第6回 『参議院と憲法保障 二院制改革をめぐる日英比較制度論』
田中祥貴(法学部教授)
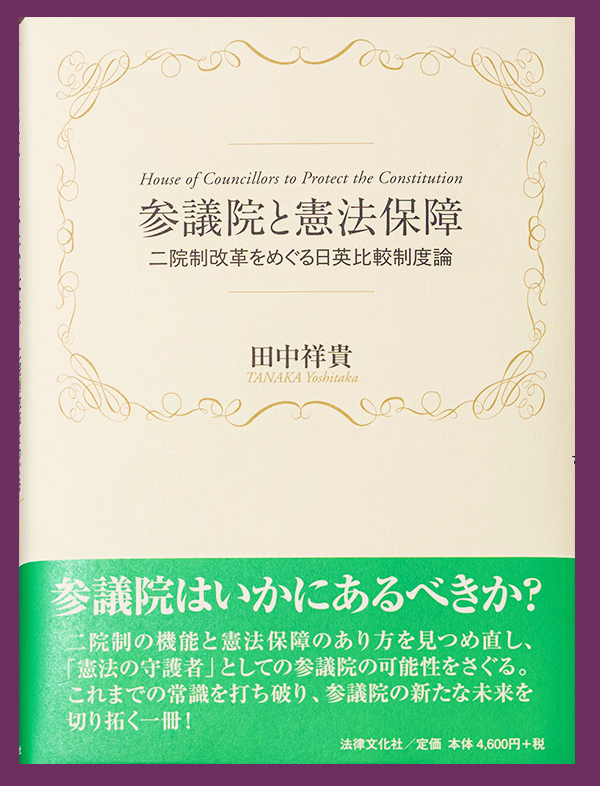
長期的な視野での議論が期待され、「良識の府」と呼ばれる参議院。時に参議院廃止論が話題になりますが、本来、参議院はどうあるべきなのでしょうか。その参議院と委任立法をテーマに問題提起しているのが『参議院と憲法保障 二院制改革をめぐる日英比較制度論』(法律文化社)です。本書を執筆した法学部の田中祥貴教授に聞きました。
■参議院はいかにあるべきかを問う
2021年10月に発行された『参議院と憲法保障 二院制改革をめぐる日英比較制度論』は2022年度日本公共政策学会 著作賞を受賞され、高く評価されています。本書では「参議院はいかにあるべきか」について大胆な改革案が提示されていますが、まず、その内容を簡単にお聞かせください。
「参議院はいかにあるべきか」、これは憲法学でも長らく難問とされてきました。実は、憲法ではその点に言及する規定がなく、現在でも参議院の役割は「謎」のままです。その結果、参議院の向かうべき方向性に様々な意見があります。もっとも、参議院の方向性は、衆議院の役割との相関関係で規定する必要があります。現状は、衆議院も参議院も同じような選挙制度で選ばれ、同じような党派構成になっています。これでは衆議院が2つあるようなもので、参議院廃止論(一院制論)が出るのもやむを得ないと思います。憲法上は議院内閣制の下、衆議院には政府を創出し維持する機能が与えられ、いわば政府と衆議院は一体化した存在ですから、参議院はそれとは一線を画する存在であるべきです。私は、参議院が独自性を発揮するには、党派性の抑制が「鍵」だと考えています。参議院は、衆議院のように党派の支配を受けず、客観的・合理的な視点から「憲法の守護者」として、政府を統制する議院であるべきです。私は、その役割を参議院の「憲法保障機能」と呼んでいます。本書には、そのための改革案をいろいろと書かせていただきました。
 本著書では2022年度日本公共政策学会 著作賞を受賞した
本著書では2022年度日本公共政策学会 著作賞を受賞した
憲法保障というと、裁判所の役割のように思えます。
憲法上、違憲立法審査権が与えられた裁判所が憲法保障を担う機関であることは疑う余地がありません。しかし、現実的に裁判所が審査できるのは、具体的な権利侵害が発生して事件になっているものだけで、厳格な訴訟要件をクリアした案件のみです。多くの事案がこの訴訟要件ではねられ、訴訟の対象にもなりません。そして、訴訟要件をクリアしても、日本の裁判所には司法消極主義という法文化があり、違憲審査を避ける傾向が見られます。現在の憲法が施行された1947年以降、日本の最高裁が違憲判決を下した例は11件しかありません。同時期に憲法が施行されたドイツの違憲判決は600件を超えるので、その消極的な姿勢は顕著といえます。憲法保障に関して裁判所の役割は否定しませんが、それだけで十分といえるでしょうか。少なくとも、具体的な事件が発生する前の段階で、抽象的に法令の違憲審査をする仕組みがないのは制度的欠陥だと思います。それを参議院が補完するべきです。

先ほど、参議院廃止論(一院制論)という言葉が出ましたが、現在の日本ではしばしば有力に主張されます。
確かに、国会中継を見ていると、衆議院でも参議院でも同じような審議ばかりしていて、無駄なようにみえます。残念ですが現状のままでは、一院制論はますます優勢になっていくでしょう。それでもなお、私は二院制を支持しています。政府の政策について、その軽率や過誤を是正できるブレーキ役は必要だからです。肝心なことは、どうすれば参議院を意義のある組織に改革できるかです。「上院は、下院に一致するなら無用であり、下院に反対するなら有害だ」と言われるジレンマの状況から参議院を解放できる方向性を模索する必要性があり、本書の提案はその一つです。英国のように専門家集団によって構成される参議院が、「憲法の守護者」として客観的・合理的な視点から政府統制の役割を果たすことができれば、その存在意義は否定し得ませんし、まさに「良識の府」「理性の府」にふさわしい機能となるのではないでしょうか。
 参議院議場(提供:参議院)
参議院議場(提供:参議院)
2022年の参院選では、「参議院は多様な民意を反映すべきで、特にジェンダー平等の観点から議員の比率を男女で均等にすべきだ」という議論がありましたが、どうお考えですか。
参議院内の多様性の確保は重要です。ただし、憲法43条では、参議院議員も含め、すべての国会議員は「全国民の代表」と規定されています。男性の代表でも女性の代表でもありません。人間には様々な属性があります。男女同数でなければならないという考え方でいけば、LGBTQ+の方々はどうなるのでしょうか。本来、憲法は属性に関わりなく、男性であれ、女性であれ、すべての人がかけがえのない尊厳を持った個人として尊重されることを求めています。我々が目指すべき社会とは、そのような属性による区別を超えて、すべての人が尊重される社会ではないでしょうか。
■委任立法をチェックしない日本
本書のもう一つのテーマが「委任立法」です。「委任立法」とは、本来なら法律に定めるべき事項を行政に委ねることを指しますが、その内容を具体的に教えてください。
日本では多くの人が、法律を国会が制定していると信じているでしょう。しかし、その認識は事実とは異なります。多くの場合、法律には具体的な内容を書き込まず、すべて後から行政府の政令や省令等で制定できるように、国会が立法権を行政府に委任しているのです。実際、日本の法律は国会議員ではなく、行政官僚によって作られているといって言い過ぎではありません。その結果、日本の法律は、政省令と照らし合わさなければ、その内容が理解できないのが実情です。例えば大学を例にすると、この国の大学教育がいかにあるべきかを、国会で審議して学校教育法という法律で規定しているかというと、そうではありません。具体的な内容は、大学設置基準という文科省の命令で定められるように、必要な権限がすべて行政府に委任されているのです。もちろんこれは教育だけではなく、経済、金融、産業、医療、社会福祉など、あらゆる政策分野で日常化しています。
 国会議事堂(提供:参議院)
国会議事堂(提供:参議院)
委任立法は、いけないものなのでしょうか。
委任立法自体がいけない訳ではありません。現実の行政には、迅速性・機動性が求められたり、専門性・技術性が求められたりする局面が多々あります。例えば、新型コロナ感染症対策を例に挙げますと、度重なる新型株の出現によって時々刻々と大きく変化する感染状況に対応するためには、毎回法律を改正していたのでは間に合いません。また、適切な対応をするにも専門外の国会議員には困難で、やはり専門的知見が要求されますが、それは専門性・機動性に優れた行政府に委ねた方が目的に適っています。そこで、新型インフルエンザ特措法、感染症法や検疫法等の法律において、政省令への広範な立法権委任という手法が大いに活用されました。もちろん、それは必要かつ合理的な措置といえます。

ただし、他方で、移動の自由や経済活動の自由など、多くの国民の基本的人権が制約を受けたことも記憶に新しいところでしょう。だからこそ、人権保障という観点からは、何でも行政府に丸投げで「どうぞご自由に!」ではいけないのです。法治国家では、国民の法的権利や自由を制限できるのは法律のみと理解されています。法律は国民の代表である国会がチェックするからです。その基本原則を忘れてはいけません。少なくとも、国民の権利や自由を制限する行政の委任立法は、国会のチェックを経る必要があるというべきです。
このことを少し、別の観点からお話しましょう。歴史を振り返ると、ヒトラー率いるナチス政権は全権委任法という法律を制定し、あらゆる立法権を政府に委任させることで独裁体制を確立したのです。その結果、ドイツでは計り知れない人権侵害が繰り返されました。同様に、戦前の日本でも国家総動員法という法律で戦時国家体制の確立のために、必要な事項を行政命令で定められるように立法権をすべて政府に委任させ、ファシズム法体制を確立した経緯があります。立法権委任という手法は、そういう非常に危険な側面を常に持っているのです。歴史からの教訓を忘れてはいけません。ですから、政府への立法権委任を安易に認めるべきではありません。権力が政府に集中することは非常に危険です。平時から、その認識を忘れず、「権力分立」の意義を振り返ってみていただきたいです。
諸外国でも、委任立法は行われているのですか。
もちろん、委任立法が活用されているのは、日本だけではありません。ただし、日本の国会は、本来、法律で定めるはずの事項(人権制限等)の定立を行政府に委任した後、委任立法でどのように定められたのか事後的にチェックしていません。この点、世界に目を向けると、委任立法をまったくチェックしていない国は、先進国の中では日本くらいです。日本の国会議員はこの状況にまったく問題意識を持っておらず「細則は行政命令で定めるのが常識だ」といいます。「日本の常識は世界の非常識」という典型例といえます。特に、先進国の中でも、英国は委任立法の統制に積極的です。委任立法は、議会制民主主義を空洞化させる深刻な憲法問題だと認識されているのです。これらの先進国の例にならって、日本も委任立法で空洞化した議会制民主主義を再生する道を検討するべきです。
 英国議会
英国議会
■リベラルアーツを学び、常識からの解放を
最後に、田中先生が憲法学に興味を持ったきっかけをお聞かせください。
憲法学への興味は、私の生い立ちと関係があります。私の父は超保守的な人で、「自分の利益など考えず、お国のために何ができるかを考えて生きるように」と言われて育ちました。将来は、「お国」のために生きなければならないと信じていました。ところが、大学に入って憲法の基本書を読んでみると、国家は国民のために存在し、また、個人の人権保障こそが最も大切だと書いてあったのです。今まで教えられてきた価値観とは真逆の内容で、全身を雷に打たれたような衝撃を覚えました。それまで私を縛っていた「常識」から解放された瞬間でした。
学問を修めることで、これまでにない新たな視点や価値観が養えます。それは、学生の皆さんにとっても自分の世界を広げることにつながります。様々な視点から考察できるようになることで、従来の「常識」が常識ではなくなり、もっと自由で開かれた発想ができるようになるでしょう。大学の学びではリベラル・アーツ(liberal arts)の修得を重視しています。その語源はラテン語のアルテス・リベラレス(artes liberales)で、リベラレスとは「解放する」という意味です。ぜひ、学問を通じて自分自身を解放する体験をしていただきたいと願っています。

プロフィール)
たなか・よしたか/1970年大阪市生まれ。2002年、神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了/博士(法学)。信州大学学術研究院総合人間科学系全学教育機構准教授、参議院憲法審査会客員調査員などを経て現職。専攻は憲法学・比較憲法学。単著に『委任立法と議会』(日本評論社、2012年)があるほか、共著に『“改革の時代”と憲法』(敬文堂、2006年)、『新・エッセンス憲法』(法律文化社、2017年)、『憲法理論とその展開』(信山社、2017年)などがある。
