第7回 『近代社会と個人<私人>を超えて』
竹内真澄(社会学部教授)
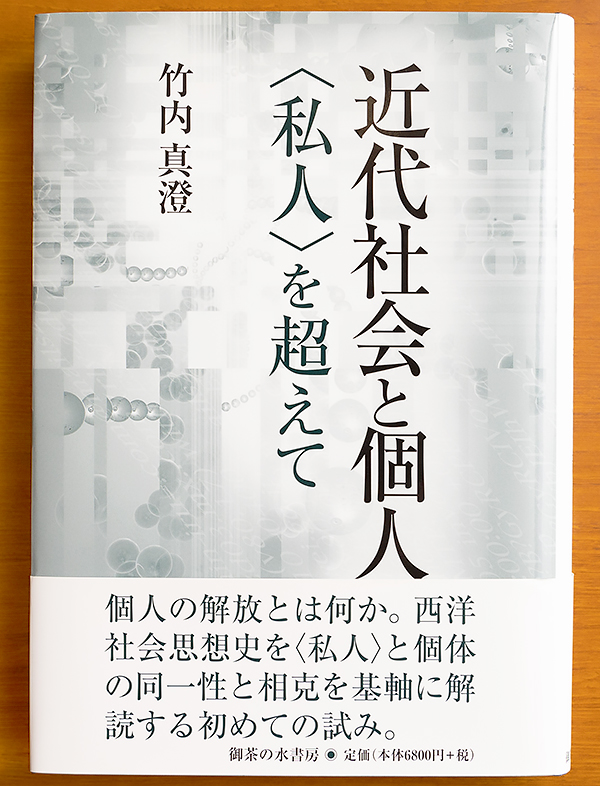
10代の頃から、個人に強い関心を持っていたという社会学部の竹内真澄教授。内なる問いに端を発し、西洋社会思想史の約500年を読み解いた著書『近代社会と個人<私人>を超えて』(御茶の水書房)を2022年に出版しました。本書への思いを聞きました。
■西洋社会思想史を500年の流れで解明
まず、竹内先生の著書『近代社会と個人<私人>を超えて』を出された目的をお聞かせください。
私が大学に入った1970年代前半、社会科学や人文科学では、「近代的個人になることが非常に大切だ」と言われていました。私は18歳くらいから、個人ということに強い関心を持っているのですが、当時の周りの学生たちは個人よりも社会や政治について考えていて、物足りなさを感じていたんです。時代の空気とは別に、色々な思想の本を読んでいくと、「近代的個人というのはもう古い。近代的個人を捨てて、次の新しい個人に進まないといけない」というようなことが書いてありました。近代的個人になるべきか、それとも捨てるべきか。ずっと疑問を持ってきました。そこで、自分自身の個人についての関心に決着をつけようと、ここ500年分くらいの西洋社会思想史をたどることにしたのです。近代的個人を樹立する動きと、近代的個人を乗り越える動きを約500年の流れで捉え、あれこれの人物がではなく、500年という構造が何を言おうとしているのかを本書で解明することにしました。
 自分自身の個人についての関心に決着をつけるため、500年に及ぶ西洋社会思想史をたどることにしました
自分自身の個人についての関心に決着をつけるため、500年に及ぶ西洋社会思想史をたどることにしました
本書は、「私人」と「個体」が大きなキーワードになっています。私人と個体と聞くと、同じような意味に思えたので、そもそも違うものだということに驚きました。それぞれの概念について、ご説明いただけますでしょうか。
私人と個体というのは、英語で言うとprivate personとindividualです。個体というのは私人に対峙した意味での個人のことですが、私人とはっきり区別させるために私は使っています。
私人というのは、「私の欲望にしたがって生きる人」という概念です。ギリシャ的な思想からすると、「本来人間は、公のために、あるいはお国のために働くべきもので、私の欲望のために生きるなどけしからん」と考えられていました。ところがホッブズ(イギリスの哲学者・政治思想家。1588~1679年)は、それまでの古代・中世の人たちの考え方を根こそぎひっくり返し「みんな私人として生きていこう」と言ったのです。この人なしに、現在の私たちの生活はないと言っても過言ではありません。職業や居住地を選べ、好きな人と暮らせるという意味で私人であることは進歩的です。自己決定の自由があるからです。ところが、19世紀の産業革命以降の資本主義では、賃労働者は自己決定を狭く制約されています。雇用されている人にとっては上司や社長がいて、やりたくない仕事でも生活のためにやらざるを得ないわけです。「我何人にも仕えず!」という思想を持つと、近代社会ではとても生きづらくなります。私人であっても、思い通りには生きられない。
これに対して個体をわかりやすく言うと、やりたいこととやっていることが合致している人間のことを意味します。例えば、「ギターを弾いて生きていきたい」という学生がいたとします。ところが路上ライブをしても人が集まらず、30代になってしまった。でも、「世間にどう思われようが、自分はギターで生きていく!」というのならば、彼は個体なのです。
なるほど。身近な例で示していただくと、私人と個体の違いがイメージできます。
この約500年の西洋社会思想史の中で、やりたいことと、実際にやっていることが合致するのが1番理想的だ、ということをはっきり言ったのがカント(ドイツの哲学者。1724~1804年)です。自律した理性を持ち、やりたいことを仕事の中でも実現させることをよしとします。ここでいう自律は、自分の指図によって自分の行動を律する、という意味です。ところがカントは、奉公人や女性などは経済力がなく、主人に抱え込まれている人たち、内属といいますが、そのような人たちは仕事や生活の中でやりたいこととやっていることを統一できていない、と言います。残念ながら理想と現実は違う、というのです。では、万人がやりたいことと、やっていることを合致させるにはどうすればいいのか。この課題は、カント以降、現代に残されています。
 西洋社会思想史は、「私たちは、どうあるべきか」という究極の問いに、各時代の巨匠たちが取り組んだ魂の記録でもあります
西洋社会思想史は、「私たちは、どうあるべきか」という究極の問いに、各時代の巨匠たちが取り組んだ魂の記録でもあります
私的なものと個人的なものは違う
本書は、私人と個体の同一性と相克を基軸にして分析されています。このような思想史分析が注目されてこなかったとのことですが、その理由は何でしょうか。
簡単に言うと自由主義の幻想の中で人が生きているからです。私人を発見したホッブズから、スミス(イギリスの経済学者。1723~1790年)までの120年間くらいは、私人のprivate personと個体のindividualはイコールであると考えられてきました。その考え方はアメリカに伝わり、私的なものは個人的なものであるという考えが全世界の19、20、21世紀をリードします。日本でも福沢諭吉から始まり、現代の主流派知識人も同じように考えているのです。しかし私は、ルソー(フランスの啓蒙思想家。1712~1778年)、カント、ヘーゲル(ドイツの哲学者。1770~1831年)の思想史の流れの中で、私的なものと個人的なものは違うという重大な異議申し立てに気づいたのです。とりわけ、ヘーゲルは、私人private personは社会的絆を失った人間、個体individualは人間同士の絆を持ちうる人間であると、中身がまったく逆だとして、個体になりたければ私人を超えなければならないという思想を展開しました。私はカントの言う自律への希望と、ヘーゲルの、私人から個体へと移行するのだという問題提起は、両方が絡まり、次の世代の思想家に受け継がれていくことになったのではないかと読み取ったのです。こういったことから、私人と個体の同一性と相克を基軸に500年間を分析しました。
私的な人間から個体的な人間にならなければいけない、というこの問題提起は、先に言いました、私が大学生だった1970年代の日本で言われた「近代的個人にならなければいけない」という問題と密接に関係しています。つまり、ヨーロッパでは18世紀に私人から個体へと目標設定を変えなければいけない、という問題提起がされていたのに、日本は戦後になってもなおホッブズやスミスが目標とした、私的人間であることによって個人にならなければならないという目標を追いかけていたわけです。「近代的個人を超えなければいけない」という問題提起は西洋ではフランス革命の後くらいから言われ始めますが、日本がその問題に直面するようになるのは1970年代後半くらいからだと思います。私が学生時代に悩んだ問いの答えは、この本を書くことでようやく見つけられました。
ホッブズ、ロック、ルソー、スミス、カント、ヘーゲル、マルクス、ハイエクら8人の西洋社会思想史の巨匠が登場しますが、竹内先生が特に興味を持たれるのは誰ですか。
私にとってはそれぞれの思想家が面白いのですが、私人を発見してそれまでの人類の歴史をひっくり返したホッブズと、ホッブズが立てた原理原則をひっくり返したマルクス(ドイツの経済学者・哲学者・革命家。1818~1883年)です。
ホッブズのいう私人は民間人ですから、政治家や役人は私人から選べばいいということになります。民間で活動する民間領域と、役人や政治家の公的領域の二つがあり、市場経済や代表制民主主義が合わさった仕組みができるのですが、これを公私二元論といいます。
この公私二元論を壊すと言い始めるのがマルクスです。
フランス革命はまさに公私二元論を確立するための革命でしたが、今度はそれを廃止することが人類の課題であるというわけです。人類が滅亡することなく生きていくには、公私二元論を維持するのか、それともやめるのかという問題に、遅かれ早かれ直面すると私は思っています。過去の社会思想史を分析し学ぶと、今生きている私たちの基本的な仕組みを言い当てているのがわかりますし、未来を展望する場合にも役立ちます。
 社会思想史を分析すると、現代の私たちの仕組みだけでなく未来の展望にも役立ちます
社会思想史を分析すると、現代の私たちの仕組みだけでなく未来の展望にも役立ちます
では、現代に生きる私たちが幸せに暮らすには、どのような意識を持てばいいでしょうか。
私人というのは、「私が私が」と利己心で行動する排他的な人間なんです。例えば、「勉強の仕方を教えて」と友だちに言った子どもが、「企業秘密だから言えない」と断られるということが身近にありました。これは、私人のモデルが小学生に入り込んでいるのです。
自分の通知表の成績を上げるには、誰にも教えない、排他的でないといけない、というわけで、人間が私人化しているのです。小学生だけでなく、学費をもらって知識を専売する大学も、その大学で給料をもらっている私自身も私人化している。だから、ひとり一人の人間も学校も企業も国家も皆私人の原理で動いているわけです。私人の原理で動かなければ損をする社会になっていますから。
このような現行のシステムについて、現代思想家の柄谷行人(1941~)は、「戦争・環境破壊・経済的格差」を生み出さずにはおかないと言っています。ひとり一人の人間、学校、企業、国家のあり方が全部集積してこれら3つの問題を生み出しているのです。私は、人間が私人から個体にならない限り、直面するこの深刻な問題を是正することはできないと思っています。
状況を少しでも変えるために、私たちが身近にできることは、言いたいことを言うことでしょう。自分の言いたいことを頭の中で考えて決め、それをねじ曲げずに「私はこう思う」と相手に伝える。一人の場面、二人の場面、公の場面いずれにおいても言い切ることが大事です。そういう訓練を1週間、1カ月、1年間と積み重ねていくといいと思います。それが個体を鍛えてくれる。
非西洋的な思想を持つ人をアジア人の立場で研究
竹内先生が現在、取り組んでいる研究を教えてください。
2022年8月に今回の本を出してから、どのような研究をすればこれから先の人生を面白おかしく生きていけるか考えました。近代の西洋社会思想史は自分なりに読み解けたので、今度は非西洋的な感受性や思想を持つ人を対象に、アジア人、日本人の立場から何がいえるかを研究しています。 例えば、日本の近代化に抵抗した夏目漱石や、韓国併合を強制した日本に抵抗し伊藤博文を撃った安重根。それから、儒教的な伝統の中でニーチェとマルクスを基礎にして中国の独立を考えた魯迅。さらに、非暴力の原理で西洋と対抗したガンジーです。ですが、今のアジアはガンジーの遺産を忘れ、インドは核兵器を持ち武器の輸入国にもなってしまっています。非暴力の原理をアジア人は受け継ぎきれていないのです。しかし、ガンジーには学ぶべきであるという西洋人もいて、例えば、ノルウェーの社会学者でガンジーを学んだヨハン・ガルトゥングは平和学について素晴らしい本を書いています。必ずこの力は強まるでしょう。そこで西欧近代思想と東洋思想ははじめて融合するのです。そのために、アジア人の一人として研究をしたいと思います。

プロフィール)
たけうち・ますみ/1954年、高知県生まれ。社会学博士。立命館大学産業社会学部卒業、立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。著書に『社会学の起源 創始者の対話』(本の泉社)、『諭吉の愉快と漱石の憂鬱』(花伝社)、『物語としての社会科学 世界的横断と歴史的縦断』(桜井書店)、『福祉国家と社会権 デンマークの経験から』(晃洋書房)、編著に『水田洋 社会思想史と社会科学のあいだ』(市民科学研究所、晃洋書房)、『石田雄にきく 日本の社会科学と言葉』(本の泉社)がある。
