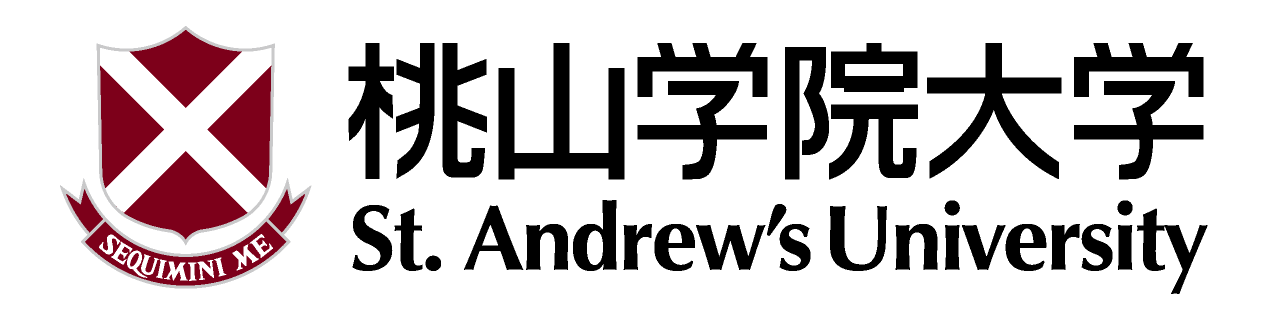1年生から英語の勉強に全力を注いでいました
私は3年生の秋学期に国際教養学部が実施する「英語セメスター留学」でシンガポールに留学をしました。
入学当初から中長期の留学に興味を持っていて、IELTSの対策や友達とスピーキングの練習をするなど、英語の勉強を続けていました。高校の時も英語に特化したクラスに入っていて、オンライン英会話などを受けていました。大学入学後も英語の勉強に全力で取り組んでいたのですが、英語が嫌いになった時期もありました。

英語の勉強に取り組む紺田さん
アジア出身の留学生との出会い
それまでは机に向かって勉強することが多く、インプット中心の学習ばかりでしたが、一度留学生と話をして見ようと思い、留学生がよく利用するヨハネホールを訪れました。そこでたまたまアジア出身の留学生と知り合いました。
その留学生と話をしているときに「英語を勉強している日本人学生は欧米圏の留学生としか交流しないことが多い。英語が話せるかどうかを見た目で判断しすぎていると思う。アジアの留学生にも英語が堪能な学生はたくさんいるのに。」と言われました。
それを聞いて、確かにそのアジアの留学生も英語が上手かったし、「英語=白人」のような考え方が日本人にはあるのかなと思いました。私自身も留学は欧米圏しか考えていませんでしたが、その留学生との出会いがきっかけでアジア圏への英語留学に興味を持つようになりました。

アジアからの留学生と交流する紺田さん
非英語母語話者が話す英語が学びたくて
留学先にシンガポールを選んだ理由はいくつかありますが、主な理由の一つは、東南アジアの先進国であり、多文化共生が進んだ国だったことです。私は英語母語話者が話す英語ではなく「さまざまな国の人々(非英語母語話者)が話す英語」を学びたいと思っていたので、シンガポールはまさに私が求める環境でした。
もう一つの理由は、シンガポールには中華系、マレー系、インド系等を主とする方々が暮らしていて、一つの国の中で異なる文化に触れることができる点が留学先として魅力的だったからです。また、その国の特徴から英語を共通語としつつ、中国語やマレー語、タミル語など、それぞれの民族の言語を学ぶバイリンガル教育が盛んなことも非常に興味深く、シンガポールに留学したいという想いを一層強くしてくれました。

様々な民族・文化が共存するシンガポールの街並み1

様々な民族・文化が共存するシンガポールの街並み2
英語能力の向上に繋がった現地での授業
現地では中上級から上級クラスに入り、文法やスピーキング、ライティングを中心に学びました。先生方はアメリカ人やイギリス人といった、いわゆる英語のネイティブスピーカーではなく、シンガポール人やポルトガル人など、非常に国際色豊かでした。さまざまな英語の発音に触れることができ、特にシンガポールの英語「シングリッシュ」と呼ばれる独特の英語を体験できたのは非常に興味深かったです。
上級クラスでは毎日、グループで取り組むライティングの課題があったのですが、他のクラスメイトがどのような単語や英語表現を使っているのかを見ることができ、非常に良い勉強になりました。実際にクラスメイトが使っていた表現を翌日の課題で使用するなど、インプットとアウトプットを日々繰り返すことで語彙力やライティングスキルが格段に向上したと思います。

語学学校の先生とクラスメイトと紺田さん
勉強に年齢は関係ない
クラスには社会人の方々が多く、中には働きながら語学学校に通われている方もいました。ある方は英語で経営の修士号を取得するために語学学校に通われており、誰よりも早く登校し(授業は9時スタートだったのですが、6時には登校されていました)、前日の復習やその日の予習をされていました。
日本では大学を卒業して一旦就職すると、転職を繰り返す場合でも定年まで働くことが一般的だと思います。私も留学する前まではそれが普通なのかなと思っていました。しかし、シンガポールの語学学校で社会人の方々がスキルアップのために熱心に勉強されている姿を見て、学び続けることに年齢は関係ないんだなと強く感じました。

語学学校のクラスメイトと紺田さん
苦手だったリスニングを克服
留学を通じて、英語の4技能すべてが上達したと思います。私の場合は特にリスンニングスキルが格段に向上しました。もともとリスニングが苦手で、留学前に受験したTOEICでもあまり良い点を取ることができませんでした。
しかし、帰国後に再度受験した際には、リスニングでほぼ満点に近い点数を取ることができました。トータルの点数も約790点を取得し、留学前から大幅にスコアが上がりました。今後は留学経験を生かして大学院に進みたいと思っています。

国際教養学部 英語・国際文化学科 4年生 紺田 遥加さん
ー 番外編 ー
留学経験を生かし東ティモールのボランティアへ
留学から帰国した後、東ティモールでのボランティアに参加しました。
実は留学前に受講していた授業で、開発途上国をテーマにした講義があり、そこで初めて東ティモールについて知りました。もともと開発途上国に興味があり、いつか行ってみたいという気持ちはあったのですが、なかなか機会に恵まれませんでした。
そんな中、帰国後の夏休みにたまたま見ていたSNSで東ティモールのボランティア募集広告を見つけ、「これだ!」と思い、ダメもとで応募したところ採用されました。
おそらく留学前の私なら、SNSで東ティモールの広告を見ても「ああ、東ティモールでボランティアをしているんだ」と思うだけで、実際に申し込むことはなかったと思います。しかし、シンガポールに留学をしたことで、英語力もそうですが、自分に自信がつき、参加を決断する勇気が持てました。そのような意味では、留学は単に語学力を伸ばすためのものだけではなく、自分自身を成長させてくれる体験なんじゃないかなと改めて思います。

東ティモールのボランティア参加者と紺田さん
東ティモールで見つけた豊かさのかたち
大統領府内にあるフリースクールや首都にあるインターナショナルスクール、農村の小学校に赴き、現地における教育の現状について学びました。
現在の社会では、テレビやインターネットを通じて、東ティモールのような開発途上国の情報にも簡単にアクセスできるようになっています。実際、テレビのCMなどで海外の子どもたちが飢餓や健康問題、環境汚染などに苦しむ様子を目にすることもあります。
もちろん、そうした現状があるのは事実ですが、開発途上国のすべての人々がそのような問題に苦しんでいるわけではありません。実際、私が東ティモールの現地で見たのは明るく元気に過ごす人たちの生き生きとした表情でした。東ティモールは、日本のように多くの物資や技術、整った教育環境があるわけではありませんが、その国に住む人々の表情は活気に満ち溢れ、幸せそうに見えました。
このボランティアを通じて、物質的な豊かさが必ずしも精神的な豊かさに繋がるというわけではないんだということを実感しました。

東ティモールでのボランティアの様子1

東ティモールでのボランティアの様子2

東ティモールでのボランティアの様子3

東ティモールでのボランティアの様子4