
SAインタビュー
実際に、SA(スチューデント・アシスタント)として活躍した学生に、自らの経験を語ってもらいました。
2015年度 「特集 教員・SA・受講生と語るSAの効果」
「FD NEW vol.8」には紙面の都合で掲載できなかった話題です。「FD NEW vol.8」はこちらから
司会・インタビュアー 田中 志津子(法学部教授・全学FD推進委員会 委員)
| 出席者 | SA | 奥宮 修斗さん(経済学部4年次生) |
| 受講生 | 井上 雄登さん(経済学部2年次生) | |
| 加尻 尚也さん(経済学部2年次生) | ||
| 中原 章吾さん(経済学部2年次生) | ||
| 担当教員 | 吉田 恵子(経済学部准教授) |
SAと交流しよう
司会:パワーポイントを添削するやりとりは吉田先生を経由するのですか。
吉田:いえ、奥宮さんと受講生に直接やりとりしてもらっています。SAの裁量に任せること、受講生には普段交流の無い先輩と接してもらうことも狙いました。
井上:先生に提出する前に奥宮さんに見てもらいます。
吉田:奥宮さんは毎週水曜日に夜行バスで東京の内定先の企業研修に行っています。木曜の朝に夜行バスで帰ってきて、木曜日2時限の「コース演習」のSAを担当してもらっています。
奥宮:直前に添削の依頼が来ることもあります。木曜の朝にメールが来ていてすぐ添削し送信し、受講生が1時限終わりの休み時間に作業したりとか。
加尻:すいません。提出が遅くなることもありました。
授業への効果—「第三者目線」での俯瞰
司会:SAを採用して授業がよくなったことはありますか?
吉田:すごくあります。先ほど受講生が緊張感と言っていましたが、私自身もすごく感じる時があります。ちゃんとがんばらなきゃ、という気持ちが空回りしている時に、教員でも受講生でもないSAがいることで、私も第三者的視点を持つことができます。SAから見て今の演習はどういう状態なのだろうと私自身が振り返ることができるようになりました。
それから、教員をしていると学生の気持ちがわからなくなってしまうことがあります。SAからコメントも頂きますので、今学生が知りたいことを何かプラスアルファできるだろうかと考えます。
司会:わかります。私たち教員は変わらず大学にいますが、学生さんは卒業していき、年齢の差も開いていきますから。
吉田:そうです。そんな時にこれまでの授業と違うトピックスとして奥宮さんが自分からしてくれたことがあります。
SAからの自発的提案—授業を超えた「先輩」から「後輩」へのアドバイス
吉田:奥宮さんは就職活動中からSAを担当してくれたのですが、就職活動を終えて自分が就職活動をする前にこんなことをしていたらもっと良かったのにと思うことがあるので授業で話したいと提案してくれました。A4のプリントを作成してきて「これをみんなに伝えたい」と。
奥宮:大手広告代理店が出版している就職活動本のようなものを読みました。大人は私たち世代をどう見ているのか、という報告があり「自分たちが大人からどう見られているのか」をわかった上で、自分はそうだなとか、自分はここが違うな、と「大人からの視点」を考えた上で自己分析をし、履歴書を書いた方が良かったのではないかと思いました。
吉田:受講生全員が受けとめた訳ではないとは思いますが、何人かは「そうか」と感じ、波及効果がありました。彼の発見した事を2年次生たちに伝えることができたということ、そういう意味で彼の存在によって、私では絶対できなかった授業の内容を改善できたのではないか。私自身も「他の大人の視点」という点はなるほど、と勉強させてもらったと思います。
2012年度 「SA(スチューデント・アシスタント)経験を語る!」
①「大学入門セミナー」におけるSA制度の利用—上級生から下級生へ伝える「有意義な大学生活の過ごし方」—
②「基礎演習」(合同形式)におけるSA制度の利用-模擬裁判の経験を通して、人に伝えることの楽しさや難しさを学ぶ—
①「大学入門セミナー」におけるSA制度の利用 —上級生から下級生へ伝える「有意義な大学生活の過ごし方」—
国際教養学部准教授 和栗珠里先生、中川美弥さん(国際教養学部4年次)
新田華枝さん(国際教養学部4年次)、河合亜樹さん(国際教養学部4年次)
—どの科目でSA制度を利用されましたか?——
和栗先生:「大学入門セミナー」という1年生の基礎演習科目の2回目の授業で、大学での授業の受け方や大学生活の過ごし方などについて、先輩の体験に基づいた話を聞く機会として導入しました。
—SAとしてどんな仕事をされましたか?——
中川:自分のこれまでを振り返り、有意義な大学生活の送り方について話しました。いろいろな異文化交流をしましたが、とくにインドネシアのワークキャンプでの経験は、就職活動にも役に立ったと思います。
河合:私は図書館司書の資格を取りたくて大学に入学したので、そのことを第一に説明しました。また、情報センターの学生スタッフとして学内で働いたり、イタリア語の短期留学プログラムに参加したりした体験について話しました。部活動・サークル活動についても紹介しました。
新田:私は、日本語教員の資格について話しました。日本語教員になるための授業を履修して、海外の大学で3週間の日本語教育実習をしたことなどです。ただ、私はヨーロッパ・アメリカ文化専修なのですが、日本語教員資格の科目は主にジャパニーズ・スタディーズ専修のものになるので、卒業に必要な単位以外に多くの単位をとらなければなりませんでした。
中川:私は反対にジャパニーズ・スタディーズ専修ですが、イタリアに興味が湧いてヨーロッパ・アメリカ文化専修のゼミに入った結果、ジャパニーズ・スタディーズの単位をそろえるのに苦労しました。だから、後悔も込めて、履修や専修の選び方に注意するように言いました。
—話してみてどうでしたか?——
河合:緊張しましたが、後輩たちが真剣に聞いてくれたので、嬉しかったです。
新田:うまく話せるか不安だったけれど、少し自信がつきました。人前で話した経験は、就職活動の面接に活かすことができました。
中川:私が1年生のときにも先輩の話を聞きたかったです。大学では、自分で動かなければ得られない情報がたくさんあって、あとから知ることも多いから、こんなふうに教えてくれたら、計画的に大学生活を充実させられると思います。
和栗先生:先輩の話は実感がこもっているし、教員では気づかないような視点からの話もしてくれたので、とても効果があったようです。
— SAのみなさんも、自分を振り返ったり、SAの経験を活かしたりすることができたわけですね。
—どうもありがとうございました。
(聞き手:経営学部教授 信夫千佳子)
②「基礎演習」(合同形式)におけるSA制度の利用 —模擬裁判の経験を通して、人に伝えることの楽しさや難しさを学ぶ—
法学部講師 早川のぞみ先生、榎本 汐莉さん(法学部4年次)、長井 春香さん(法学部3年次)、
明浄 貴幸さん(法学部3年次)、山口 勝嘉さん(法学部3年次)、松下 知美さん(法学部2年次)
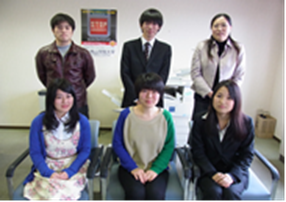
— どの授業でSA制度を導入されましたか?—
早川先生:法学部では、1回生対象の基礎演習で、SA制度を活用し、模擬裁判演習室で合同形式の模擬裁判演習を実施しました。その目的は、1回生に対して模擬裁判を見聞きさせることで、裁判の流れを理解させ、法律が裁判の中でどのように扱われるのかを学ばせることにあります。2回生以上のSAの学生には、教員指導(大久保正人先生〔刑事訴訟法〕)の下、模擬裁判を作成・実演してもらいました。
— SA業務を通じて学んだことは?—
榎本:法学部では裁判を実際に経験することがないので、これを模擬的な形で学ぶことで、裁判制度がより理解しやすくなりました。
— 難しかったことはありますか?—
榎本:1回生の学生は、大体が年下なのですが、模擬裁判の内容をどれだけ分かっているのか、彼らの様子を見ながら裁判劇を実演していくのがちょっと難しかったですね。
早川先生:模擬裁判は、一般の演劇とは異なって、法律知識が関係しますからね。
松下:私は2回生なので、1回生に1番近い立場で、どう噛み砕いたら人により分かりやすく教えられるか考えました。人を教えることによって自分も新たに学べたと思います。
山口:今回、模擬裁判において、知識の少ない学生に教える立場に回ったことで、「教えることの難しさってここにあるのか」、「こう伝えたいのに相手になんでこれが伝わらないのか」といったことを実際に体験できたことは、私にとって大きな経験になったと思います。
— 他に感想はありますか?—
明浄:僕は解説を担当したのですが、大勢の人の前で喋ることを学べたと思います。人前でハキハキ喋ることは、社会に出てから必要なスキルの一つだと思います。だから、この模擬裁判を通して得た経験をこれからの就職活動に活かしていければと思っています。
早川先生:明浄くんは模擬裁判の進行役として、裁判手続きの流れや裁判劇に登場する法律用語の意味を解説する役割を担いました。
長井:私は刑法が好きでSAに参加しました。SAの活動を通して、先生と関わる機会が多かったので、裁判劇などで分からないことなどを、休憩時間にお聞きすることもあり、学ぶことがたくさんあったと思います。刑事訴訟法は、教科書を読んだだけでは理解するのが難しい部分がいっぱいあると思いますから。
— 学生が成長した点は見受けられましたか。—
早川先生:このSA制度は、1回生とSAが教え合う関係を、またSA同士の間でも互いに教え合う関係を作り出しました。学年を超えて主体的に学び合う経験は、学生自身にとっても大切な学びの機会になったのではないかと思います。
(聞き手:経営学部教授 信夫千佳子)