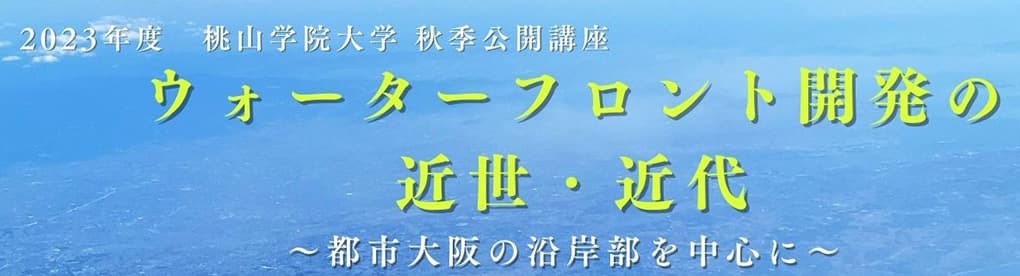
講師:島田克彦(桃山学院大学経済学部教授)
11月29日(水)15:30〜17:00に開催いたしました!
公開講座は、大学における学問研究の成果を市民の皆様に公開することを目的に1973年から毎年開催しています。本年も会場参加型とZoomウェビナーによるWeb配信の両方にて実施いたしました。
島田先生は「人間はいかに土地・空間と関係を取り結ぶか、人の土地への働きかけ」という観点から列島社会の歴史を研究されており、今回はその一環で、都市大阪沿岸部(水辺空間)を取り上げられました。
島田先生は「人間はいかに土地・空間と関係を取り結ぶか、人の土地への働きかけ」という観点から列島社会の歴史を研究されており、今回はその一環で、都市大阪沿岸部(水辺空間)を取り上げられました。

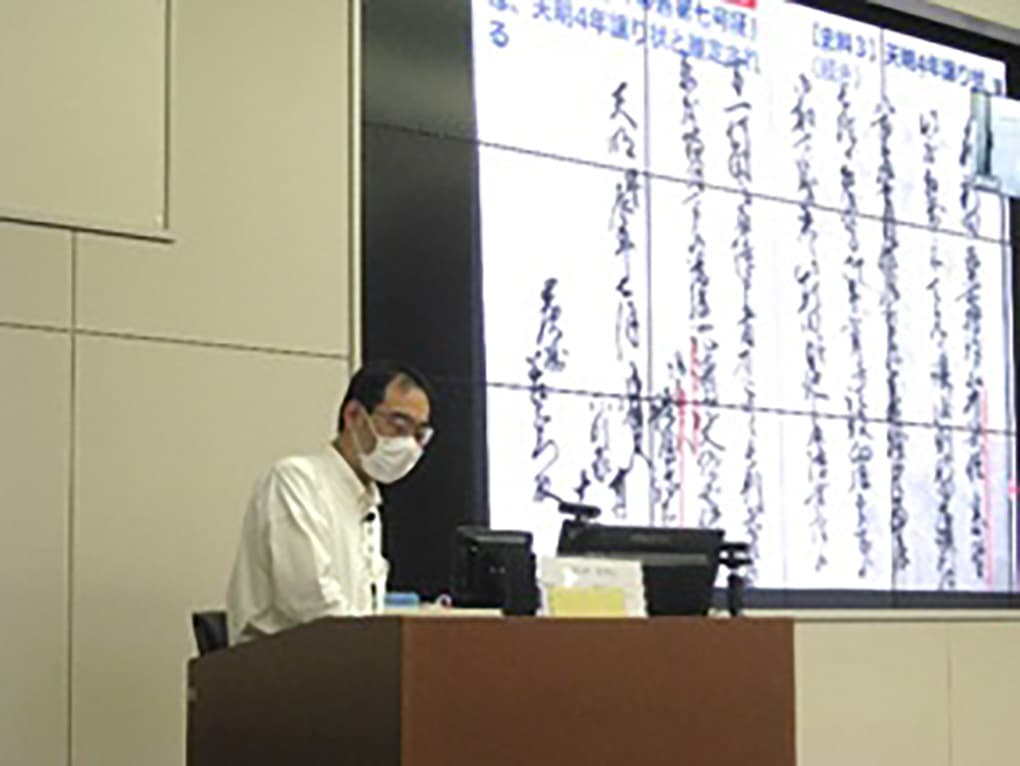
今講義では大阪湾岸新田地帯の中でも津守新田に着目し、近世から近代にかけた開発過程、そして土地の制度と所有関係の再編=法と社会の再編過程について解説いただきました。
17世紀から開発が始まった大阪湾岸新田地帯は、農業生産に特化した空間から近代的な工業地域に開発されていきます。その近世から近代への移行過程には、土地所有関係の再編が不可欠でした。
明治初期から昭和初期の地形図や、国際日本文化研究センターの民事判決原本データベースから発見した地租改正に伴う地主と小作人の紛争に関する裁判資料、また地主の手元に伝わった史料を交えながら、津守新田の歴史を読み解き、土地と人との一体性や、社会の実態と司法のあり方の相互関係について、厚みのある講義をしていただきました。
ご参加くださった方からは「『人々が耕作してきた事実が法を動かし得る』という社会のありように喜びを感じた。人間としての営みが厳然として重みを持つのだ、ということは現代に生きる我々にも勇気を与えてくれる。ローカルな歴史資料の分析から明治の国家政策(土地所有権)を論じる、地に足をつけた研究方法も素晴らしいと感じた。」などのお声を頂戴しました。
17世紀から開発が始まった大阪湾岸新田地帯は、農業生産に特化した空間から近代的な工業地域に開発されていきます。その近世から近代への移行過程には、土地所有関係の再編が不可欠でした。
明治初期から昭和初期の地形図や、国際日本文化研究センターの民事判決原本データベースから発見した地租改正に伴う地主と小作人の紛争に関する裁判資料、また地主の手元に伝わった史料を交えながら、津守新田の歴史を読み解き、土地と人との一体性や、社会の実態と司法のあり方の相互関係について、厚みのある講義をしていただきました。
ご参加くださった方からは「『人々が耕作してきた事実が法を動かし得る』という社会のありように喜びを感じた。人間としての営みが厳然として重みを持つのだ、ということは現代に生きる我々にも勇気を与えてくれる。ローカルな歴史資料の分析から明治の国家政策(土地所有権)を論じる、地に足をつけた研究方法も素晴らしいと感じた。」などのお声を頂戴しました。
ご参加くださった皆様、また、アンケートにご回答くださった皆様、誠にありがとうございました。来年度の秋季公開講座に関する詳細は、決まり次第、桃山学院大学エクステンション・センターのホームページにて、お知らせいたします。
桃山学院大学の公開講座の歴史を絶やさないよう、引き続き、皆様に学びの機会を提供できるよう努めて参ります。今後ともより多くの方のご参加をお待ちしています。
桃山学院大学の公開講座の歴史を絶やさないよう、引き続き、皆様に学びの機会を提供できるよう努めて参ります。今後ともより多くの方のご参加をお待ちしています。