第3回『20年目の世界一周 実験的生活世界の冒険社会学』
大野哲也(社会学部 社会学科教授)

「人類史は冒険史です」という社会学部 社会学科の大野哲也さんは、1993年から約5年間、自転車で世界一周を成し遂げた元冒険家。この旅で出会った人たちを約20年後に再訪し、その人生の軌跡を描いたのが『20年目の世界一周 実験的生活世界の冒険社会学』(晃洋書房)です。本書を出版した目的や、「冒険社会学」の面白さを聞きました。
■「ウロウロしている人」に興味を持ち研究
大野先生は、1993年から98年まで自転車で世界一周しましたが、そもそも、どのような旅だったのでしょうか。

もともと私は、中学校教員をしていました。その当時、休職(現職参加)して青年海外協力隊に約2年間参加し、パプアニューギニアに行きました。村人のほとんどが裸足で暮らし、時計のない生活を送り、海辺で集めた貝殻が貨幣となって芋が買えたりする文化にカルチャーショックを受けながらも、「こんな生き方があるのか!」とすごく面白さを感じたんです。帰国してから、「世界は自分の知らないことで満ち溢れている。教員をしている場合じゃないな」と思っていたら、協力隊の時の友人に「大野、自転車で世界一周したらきっと楽しいよ」と言われました。彼が自転車好きだったからですが、私は「これだ!」と思い、翌日に月末で辞めさせてもらいたいと辞表を出し、退職しました。
「アメリカ大陸を横断しよう」など、ざっくりとした目標を決め、その日の気分で適当なルートを走りました。走行距離はだいたい1日に100km。朝6時に走り始めると、昼過ぎには100kmくらいになります。その後は、寝床となる場所を探してテントを張り、村や町を散策して過ごしました。たまたま知り合った人の家に、1~2カ月間、居候することもありました。結局、5年間の間に、北米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリアの五大陸を自転車で走り、その五大陸の最高峰に登り、南極点と北極点に行ったことになります。
その世界一周の自転車旅で出会った人たちの中から5組を訪ね、彼らのライフヒストリーを紹介したのが、2021年10月に出版された『20年目の世界一周 実験的生活世界の冒険社会学』です。本書を刊行した目的を聞かせてください。
この旅で出会った人の中で、特に魅力的な生き方をしていると感じた日本人を中心に再訪し、彼らの生き様や冒険心に学術的な光を当てて、本にしたいと思ったからです。私は以前から、本拠地を離れて「ウロウロしている人」に興味を持っています。2012年には、バックパッカーを研究対象にした、『旅を生きる人びと—バックパッカーの人類学—』という単著を出しました。今回は、旅、人生、冒険心が自分の中でオーバーラップし、冒険という行為を社会学的に考えてみたいという思いもありました。
本書に登場する人たちの中で、特に思い入れのある方をあげるとすると、どなたになりますか。
和歌山県からアルゼンチンに移住した榎本理一さん、澄代さん夫妻です。実は、自転車の旅を終えた後に、「人間って面白い」と感じて文化人類学を学びたくなり、大学院に入りました。その時に修士論文に書いたのが、榎本さん夫妻の生き方です。本書で榎本さん夫妻を紹介した章は、この修士論文が元になっています。
榎本さん夫妻と最初に出会ったのは、自転車で南米を旅していた時で、長期間、居候をさせてもらいました。和歌山で暮らしていた理一さんは、榎本家の跡取りが第二次世界大戦で戦死したので財産を守るために養子に入り、澄代さんと結婚しました。裕福なイエの人だったのに、財産である山林や田畑などをすべて売り、3人の子どもを連れてアルゼンチンに移住します。なぜ移住したのか、私は何度も聞きましたが、その度に少しずつ理由が変わりました。「たくさんの台風が襲来するので農業をするのが困難になった」と言ったかと思えば、別の日には、「海外への憧れがあった」などと言います。恐らく今となっては、移住の本当の理由は、本人にも分からないのでしょう。ただ、養子に入ってまで守ろうとした財産を売り、裸一貫でアルゼンチンに移住し、騙されたこともあったけれど、最後には広大な土地を手に入れて花卉栽培で成功したのは事実です。貧困に苦しんだから新天地を求めて移住する、というような一般的な移民のイメージとは異なる、破天荒な生き方にすごく魅力を感じました。
 榎本さんご一家
榎本さんご一家榎本さん夫妻の次に登場する星和明さんは、本来の冒険家です。
南極で出会って意気投合した星さんからは、山の面白さを教わりました。山の素人だった私を北米最高峰のデナリや、ヨーロッパアルプス最高峰のモンブランに連れて行ってくれたのです。モンブランは人気が高い山で登山客は多かったですが、滑落したら死んでしまう所がたくさんありました。命がけで登って頂上に着いても、天候がいつ急変するか分からないので30分いるかどうか。頂上に立った余韻に浸る間もないですが、それでも下山すると「山って楽しいな」と思い、次はアフリカのキリマンジャロに登りました。自転車の旅もそうですが、登山は何の役にも立たないけれどなぜだか夢中になってしまう、究極の自己満足的行為ですね。
榎本さん夫妻、星さんを含む4組の人たちは、海外で何かを成し遂げたり挑戦したりする、いわゆる冒険談のイメージがありました。ところが、最後の章に登場するカナダのマイクさん一家は、小さな幸せを積み重ねる生き方を選び、冒険っぽく感じられません。しかし、本章を読み進めると、名誉や金銭的な利得への欲望を断ち切ることに挑戦し続けたことが分かりました。大きな成果を得たわけではないですが、これも冒険と捉えたのですね。
そうなんです。例えば、いい大学に進学して、いい会社に就職し社長を目指すというようなサクセスストーリーに憧れる人は多いと思います。しかし、マイクさんは社会に浸透しているそのような「上昇志向」そのものを嫌悪し、「出世物語」からは徹底的に距離を置きます。家や車を買う、いい学校に行くなどを良しとする、多くの人たちに染みわたる既成の価値観を拒否するわけです。こうした姿勢を貫くのはチャレンジで、先の榎本さん夫妻が全財産を売り払ってまでしてアルゼンチンに行ったこととスタンス的には同じ。一つの冒険、冒険心のあり方だと思いました。
■冒険心が新しい価値観を作る
本の副題にもなっていますが、「冒険社会学」という言葉を私は初めて聞きました。冒険社会学とは、どのような学びなのでしょうか。
「冒険社会学」は私が作った言葉です。社会学には、環境社会学や観光社会学などいろいろな分野があり、社会学で冒険を切り口に研究したいという思いから名付けました。私は、人類史は冒険史だと考えています。というのも、アフリカで誕生した人類が二足歩行で、てくてく歩き、ユーラシア大陸を渡り、アメリカ大陸に進出し、南米大陸の最南端まで到達するのが今から約1万年前のことで、これは壮大なプロジェクトです。彼らのこの行為を支えたのは、素朴な冒険心だと思うのです。人類の歴史は約700万年と言われますが、アフリカから南米大陸まで彼らが歩いて行ったから今日があります。つまり、冒険心がきっかけとなって、新しい価値観や新しい社会ができ上っていくのだと思っています。

人間の一生はよく旅に例えられますが、人生も冒険だという感覚を持っています。私たち人間は、いつかは必ず死にます。でも、自分がいつ、どこで死ぬのかは分かりません。死がゴールだとして、今、自分が人生のどの辺りに位置するのかも分からないわけです。そう考えると、それは一つの漂流であり、まさしく冒険です。既成概念にどっぷりと浸りながら生きていくのか、榎本さん夫妻らのように既成の価値観を打破しながら生きていくのか、冒険の仕方を選ぶのは自分次第です。
■現代社会の冒険がどう商業化されるかを明らかに
ところで、大野先生は今、どのような研究に取り組んでいるのですか。
エベレストにフォーカスして、現代社会の冒険がどのように商業化されているのかを明らかにしようと取り組み始めています。エベレストには登頂ツアーがあり、素人でもお金を出せば、必ずというわけではないですが頂上まで連れて行ってくれます。700〜800万円の料金を掲げているツアー会社が多いですが、中には当人の登山経験の質と量によって料金が変わるという会社もあり、多種多様です。コロナウイルスの感染状況が落ち着けば、今年の夏にでも現地調査に行きたいですね。
特に、モノという観点から冒険を見て、社会がどう変わるかを考えてみたいと思っています。例えば、海洋冒険家の堀江謙一さんは、1962年に太平洋を単独無寄港で横断するという人類初の快挙を成し遂げますが、この時はべニア板製のヨットに乗っていました。ベニア製ヨットが当時の最先端だったのです。でも今、堀江さんはFRP(繊維強化プラスティック)と発泡スチロールで、沈まない工夫を徹底的に施したヨットを使って冒険に挑んでいます(この取材の後、堀江さんは2022年6月4日に世界最高齢での太平洋単独無寄港横断を成功されました)。モノによって冒険は変化していくでしょうし、また冒険の仕方によってモノが進化し、社会も変化していくのではないかと考えています。
アフターコロナの世の中では、冒険はどんなふうに変わっていくと思いますか。
多くの人が素朴な冒険心を持っているはずなので、コロナウイルスの影響があっても、冒険心がなくなるということはないでしょう。ですから、冒険がしぼんでいく、とはまったく考えていません。ただ、冒険心の表れ方は変わっていくと思います。これまでの人類史では、状況に合わせていくうちに新しいことが生まれています。今、自転車ブームで、自転車に乗る人がすごく増えています。自転車でぶらぶら漂流しているうちに、新しい何かが生まれるかもしれませんね。
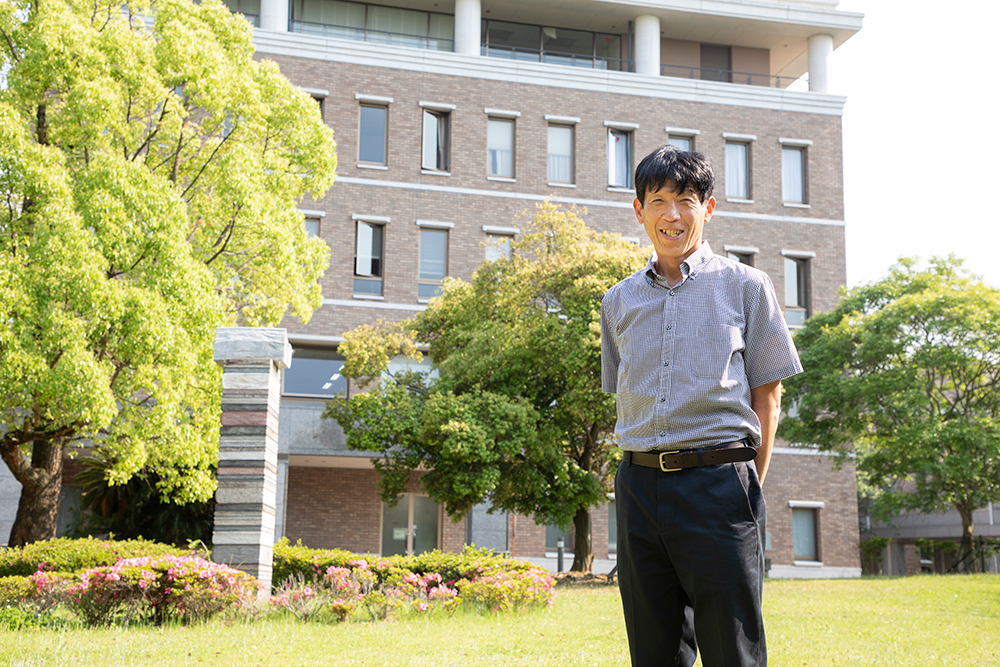
プロフィール)
おおの・てつや/1961年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程指導認定退学、博士(人間・環境学)。主に「冒険と現代社会」をテーマに研究。






