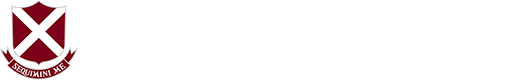プロジェクト活動概要
2025年度 共同研究プロジェクト活動概要
<23共292>
-
研究テーマ
障害者差別解消法施行後の大学における合理的配慮と学生支援(Ⅱ)
-
英文テーマ
Reasonable Accommodation and Support for College Students after the Disability Discrimination Act(Ⅱ)
-
研究期間
2023年4月~2026年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 安原 佳子 社会学部教授
- 全体総括、発達障がいのある学生支援を中心に研究会の企画
- 小松 佐穂子社会学部准教授
- 研究会の企画(教育心理学を中心に)及び取りまとめ
- 篠原 千佳 社会学部准教授
- 国内外の大学に関する情報収集、研究会への関与
- 信夫 千佳子 経営学部教授
- 障がい者雇用を中心に研究会の企画、情報収集
- 金澤 ますみ 社会学部准教授
- スクールソーシャルワークを中心に研究会の企画、情報収集
- 栄 セツコ 社会学部教授
- メンタルヘルスを中心に研究会の企画、情報収集
- 辻井 誠人 社会学部教授
- 精神障がいのある学生支援を中心に研究会の企画、情報収集
- 清水 美穗 本学非常勤講師
- スクールソーシャルワークの視点からの情報収集、研究会への関与
- 長谷川 陽一 人間教育学部教授
- 障がい学生支援の高大連携を中心に研究会の企画、情報収集
- 藤原 昌樹 人間教育学部准教授
- 教員養成の視点からの情報収集
- 葉山 貴美子 人間教育学部教授
- 教員養成の視点からの情報収集
- 永井 明子 人間教育学部准教授
- 教員養成の視点からの情報収集
- 森田 政恒 本学教務課課長
- 教務上の支援の検討
- 尾崎 博久 本学学生支援課課長
- 学生生活上の支援の検討
- 永嶺 敦史 本学キャリアセンター事務課課長
- 就職活動上の支援の検討
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
なお、研究成果については、学会での報告、成果物(論文)の作成、大学現場への提言を予定している。
共同研究の内容および効果
<23共293>
-
研究テーマ
新指導要領とデータサイエンスに対応する大学教育の理論と実践
-
英文テーマ
Theory and practice of university education corresponding to the new teaching guidelines and data science
-
研究期間
2023年4月~2026年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 藤間 真 経済学部教授
- 全体統括、情報教育
- 櫻井 雄大 経済学部講師
- ICT教育
- 井田 大輔 経済学部教授
- 経済学教育・初年次教育
- 井田 憲計 経済学部教授
- 経済学教育・統計教育
- 吉弘 憲介 経済学部教授
- 経済学教育
- 中西 啓喜 社会学部准教授
- 初年次教育・入試制度
- 萩原 久美子 社会学部教授
- 初年次教育
- 村上 あかね 社会学部准教授
- 初年次教育
- 大田 靖 経営学部教授
- データサイエンス教育
- 森下 裕三 国際教養学部准教授
- 言語学教育
- 水谷 直樹 共通教育機構教授
- データサイエンス教育
- 長内 遥香 共通教育機構契約教員
- 言語・プログラム開発検証
- 櫛井 亜衣 共通教育機構契約教員
- 言語・プログラム開発検証
- 鈴木 小春 共通教育機構契約教員
- 言語・プログラム開発検証
- 中村 恒彦 経営学部教授
- 会計学教育
- 井口 祐貴 法学部講師
- スポーツにおけるデータサイエンス
- 高良 要多 本学教務課課長補佐
- 初年次教育
研究の目的・特色
これらは、大学教育の入口と出口の両面から大学教育に変化が求められていることを意味する。
研究プログラム (計画・スケジュール)
【新規申請書記載内容からの変更】
共同研究の内容および効果
生成AIの急速な普及への対応を、共同研究の内容に加味する予定である。その結果、大学教育への生成AIの効果的な導入についての理論的・実践的知見を得るという効果を得ることを目指す。
<24共298>
-
研究テーマ
日本の大学におけるアカデミックライティング科目の 指導内容に関する調査
-
英文テーマ
A Survey on the Curriculum of Academic Writing Courses in Japanese Universities
-
研究期間
2024年4月~2027年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 三井 規裕 共通教育機構准教授
- 全体統括
- 西藤 真一 経営学部教授
- 大学教育で実施されている文献の調査
- 藤間 真 経済学部教授
- 大学教育で実施されている文献の調査
- 櫛井 亜依 共通教育機構契約教員
- 大学教育で実施されている文献の調査
- 鈴木 小春 共通教育機構契約教員
- 大学教育で実施されている文献の調査
- 長内 遥香 共通教育機構契約教員
- 大学教育で実施されている文献の調査
- 星 愛美 元本学共通教育機構契約教員
- 文献調査内容のまとめと分類整理
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
共同研究の内容および効果
<24共300>
-
研究テーマ
異文化共生に関する越境的研究
-
英文テーマ
Global Studies for Intercultural Cohesion
-
研究期間
2024年4月~2027年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 宮脇 永吏 国際教養学部講師
- フランスの現代社会と文化
- 土屋 祐子 国際教養学部准教授
- ローカル・エスニックメディア
- 今澤 浩二 国際教養学部教授
- イスラーム世界の歴史と文化
- 片平 幸 国際教養学部教授
- 日本表象をめぐる日本と西洋の交流史
- 辻 高広 国際教養学部准教授
- 中国近代の歴史と文化
- 韓 娥凜 国際教養学部講師
- 排外主義と多文化共生
- 王 其莉 国際教養学部准教授
- 外国人子供の言語使用と社会的ネットワーク
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
共同研究の内容および効果
<24共301>
-
研究テーマ
認知症の人と家族のピアサポートの場の構築
-
英文テーマ
Creating a place for peer support for persons with dementia and their families
-
研究期間
2024年4月~2027年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 杉原 久仁子 社会学部教授
- 全体統括
- 川井 太加子 社会学部教授
- 本人・家族支援
- 黒田 隆之 社会学部教授
- ピアサポート
- 栄 セツコ 社会学部教授
- ピアサポート
- 金津 春江 本学非常勤講師
- 家族支援
- 武田 卓也 本学非常勤講師
- 家族支援
- 藤原 太郎 本学非常勤講師
- 本人支援
- 馬 天生 社会学研究科博士後期課程
- 本人支援
- チョウ イクレイ 社会学研究科修士課程
- ピアサポート
- 松川 真也 社会学研究科修士課程
- ピアサポート
- 楊 少敏 社会学研究科修士課程
- ピアサポート
- 家村 哲也 桃山なごみ会家族
- 家族支援
- 飯坂 孝子 和泉市認知症機能強化型地域包括支援センター
- 地域連携
- 折田 静香 和泉市認知症機能強化型地域包括支援センター
- 地域連携
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
共同研究の内容および効果
<24共302>
-
研究テーマ
短時間計測における心拍変動評価の妥当性
-
英文テーマ
Validity of heart rate variability assessment in short-time measurements.
-
研究期間
2024年4月~2027年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 松本 直也 経済学部准教授
- 研究統括
- 竹内 靖子 社会学部准教授
- テータ取集
- 井口 祐貴 法学部講師
- 被験者コーディネーター
- 大西 史晃 経済学部講師
- 先行研究・学会発表用資料作成
- 杉 秋成 共通教育機構契約教員
- データ解析
- 川端 悠 大阪公立大学国際基幹教育機構准教授 /本学兼任講師
- データ取集・データ解析
- 小笠原 佑衣 大阪公立大学国際基幹教育機構特任助教
- データ収集
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
共同研究の内容および効果
<24共303>
-
研究テーマ
大学生における生活実態調査研究
-
英文テーマ
Survey research on the actual living conditions of university students
-
研究期間
2024年4月~2027年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 井口 祐貴 法学部講師
- 研究統括
- 大西 史晃 経済学部講師
- 研究統括補佐
- 松本 直也 経済学部准教授
- 実態調査・分析 コーチングの視点から
- 杉 秋成 共通教育機構 契約教員
- 実態調査・分析 体力・トレーニングの視点から
- 松本 大佑 共通教育機構 契約教員
- 実態調査・分析 公衆衛生学の視点から
- 豊田 郁豪 共通教育機構 契約教員
- 実態調査・分析 授業づくりの視点から
- 松元 隆秀 元共通教育機構 契約教員
- 実態調査・分析 測定評価の視点から
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
共同研究の内容および効果
<25共305>
-
研究テーマ
フィールドワーク教育の学際的研究
-
英文テーマ
Interdisciplinary research on fieldwork education
-
研究期間
2025年4月~2028年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 大野 哲也 社会学部教授
- 研究総括 冒険社会学 FW:ツーリズム
- 石田 あゆう 社会学部教授
- メディア論 FW:女性支援ボランティア
- 竹内 靖子 社会学部准教授
- レクリエーション論 FW:福祉レクリエーション
- 木島 由晶 社会学部准教授
- 文化社会学 FW:ファンとオタクの文化
- 長﨑 励朗 社会学部准教授
- メディア文化論 FW:関西文化
- 金 太宇 社会学部准教授
- 環境社会学 FW:環境とコミュニティ
- 濱田 武士 社会学部准教授
- 地域社会学 FW:農業と地域おこし
- 彭 永成 社会学部講師
- メディア社会学 FW:出版業界
- 生井 達也 兼任講師/ 国立民族学博物館 外来研究員
- 文化人類学 FW:ライブハウス・地域創生
- 植田 里美 兼任講師/大阪市長居障がい者 スポーツセンター指導員
- 障がい者スポーツ支援論 FW:障がい児・者スポーツ
- 水流 寛二 兼任講師/ NPO法人キャンピズ代表
- アレンジスポーツ支援論 FW:障がい児・者福祉
- 石田 易司 名誉教授/(社福)大阪婦人ホーム 理事長
- 助言 ボランティア論 FW:福祉ボランティア
- 福山 正和 地域連携課課長補佐
- ボランティア支援論 FW:ボランティア コーディネート
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
共同研究の内容および効果
<25共306>
-
研究テーマ
公共施設の情報公開の現状と課題
-
英文テーマ
The current status and issues of information disclosure of public facility
-
研究期間
2025年4月~2028年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 伊藤 潔志 経営学部教授
- 情報公開の倫理学的意義の考察/研究の総括
- 川口 厚 経済学部教授
- 学校の情報公開の分析
- 橋本 あかり 共通教育機構契約教員
- 学校図書館の情報公開の分析/データの処理・分析
- 水沼 友宏 経営学部准教授
- 公共図書館の情報公開の分析/論点整理
- 中村 恒彦 経営学部教授
- 公共施設の財務情報の公開の分析
- 吉弘 憲介 経済学部教授
- 財政学/地方自治体の財政情報の公開について
- 藤間 真 経済学部教授
- 数学/データ分析の妥当性について
- 井上 敏 経営学部教授
- 博物館学/博物館の情報公開について
研究の目的・特色
研究プログラム (計画・スケジュール)
共同研究の内容および効果
<25共307>
-
研究テーマ
日本における福祉国家の形成過程—社会問題とそれへの対応の諸相
-
英文テーマ
How are social policies developed in Japan ?!
-
研究期間
2025年4月~2028年3月(3ヶ年)
研究スタッフ、研究課題および 役割分担
代表者
- 小島 和貴 法学部教授
- 日本行政史
- 見浪 知信 経済学部准教授
- 日本経済史
- 永水 裕子 法学部教授
- 医事法、人権
- 鈴木 康文 法学部講師
- 西洋法制史
- 島田 克彦 経済学部教授
- 日本都市史
- 瀧澤 仁唱 本学名誉教授
- 労働運動、労働法
- 天本 哲史 法政大学社会学部教授
- 行政法
- 松澤 俊二 社会学部准教授
- 近・現代日本とプロレタリア
- 松本 未希子 名古屋経済大学法学部准教授
- 行政法
- 向村 九音 元非常勤教員
- 日本史