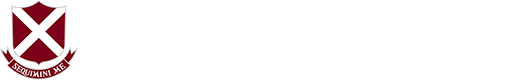学術出版助成による刊行物
個人研究および共同研究による成果を,図書として発刊するために出版経費の補助を行っています。
これまでに学術出版助成を受け出版された図書を以下に紹介します。
※横スクロールで全てご覧いただけます。
| No | 著者 | 書名 | 出版社 | 出版年 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 木島 由晶 | 好みで満ちてゆく社会—聴く・遊ぶ・愛でる・移動する文化の社会学 | 勁草書房 | 2025.12 |
| 118 | 辻本 法子 | インバウンド新時代の進化する観光土産マーケティング | 同文舘出版 | 2025.11 |
| 117 | 島田 克彦 | 近代日本の地域社会における土地所有構造 | 日本経済評論社 | 2025.10 |
| 116 | 松澤 俊二 | 「つながり」がよむ—近代和歌・短歌の社会史— | 明治書院 | 2025.10 |
| 115 | 村中 淑子 | 「ののしり」の助動詞でなにが表現されるのか—関西方言話者の表現の特質を求めて | ひつじ書房 | 2024.12 |
| 114 | 吉弘 憲介 | アメリカにおける産業構造の変化と租税政策—クリントンからトランプ、バイデン政権まで | ナカニシヤ出版 | 2024.12 |
| 113 | 大野 哲也・竹内 靖子 石田 あゆう・木島 由晶(編著) | ヘルスリテラシーの諸相—メディア・スポーツ・ウェルネス | 晃洋書房 | 2024.12 |
| 112 | 村上 あかね | 私たちはなぜ家を買うのか—後期近代における福祉国家の再編とハウジング | 勁草書房 | 2023.12 |
| 111 | 島田 勝正 | 「気づき」をうながす文法指導—英語のアクティブ・ラーニング | ひつじ書房 | 2022.12 |
| 110 | 竹内 真澄 | 近代社会と個人 <私人>を超えて | 御茶の水書房 | 2022.8 |
| 109 | 角谷 嘉則 | まちづくりのコーディネーション | 晃洋書房 |
2021.12 |
| 108 | 大野 哲也 | 20年目の世界一周 | 晃洋書房 | 2021.10 |
| 107 | 田中 祥貴 | 参議院と憲法保障ー二院制改革をめぐる日英比較制度論ー | 法律文化社 | 2021.10 |
| 106 | 濱村 純平 |
寡占競争企業の管理会計ー戦略的振替価格と多元的業績評価のモデル分析ー | 中央経済社 | 2021.9 |
| 105 | 上田 修 | 生産職場の戦後史ー戦後日本における重工業の発展と技術者・勤労担当者の取り組み | 御茶の水書房 | 2020.12 |
| 104 | 村中 淑子 | 関西方言における待遇表現の諸相 | 和泉書院 | 2020.12 |
| 103 | 望月 和彦 | 金融政策とバブルー大正期における政党政治の「始まり」と「終わりの始まり」ー | 芦書房 | 2020.12 |
| 102 | 辻本 法子 | インバウンド観光のための観光土産マーケティングー中国人消費者の購買行動ー | 同文舘出版 | 2020.12 |
| 101 | 小澤 義昭 |
監査実施プロセスの理論と実践 | 中央経済社 | 2020.9 |
| 100 | 天本 哲史 | 行政による制裁的公表の法理論 | 日本評論社 | 2019.12 |
| 99 | 大島 一二 | 朝日緑源,10年の軌跡ー中国における日系農業企業の挑戦ー | 農林統計出版 | 2019.12 |
| 98 | 望月 和彦 | 甦る国際権力政治—ポスト・グローバリゼーションと日本 | 芦書房 | 2019.12 |
| 97 | 松村 昌廣 | 日米同盟と朝鮮半島—国際政治における格闘場 | 芦書房 | 2019.11 |
| 96 | 中村 勝之 | 学生の「やる気」の見分け方 | 幻冬舎 | 2019.8 |
| 95 | 青野 正明 | 植民地朝鮮の民族宗教—国家神道体制下の「類似宗教」論 | 法藏館 | 2018.11 |
| 94 | 南出和余・木島由晶 | メディアの内と外を読み解く-大学におけるメディア教育実践 | せりか書房 | 2018.10 |
| 93 | 栄 セツコ | 病いの語りによるソーシャルワーク | 金剛出版 | 2018.10 |
| 92 | 青野 正明 | 帝国神道の形成—植民地朝鮮と国家神道の論理(翻訳) | ソミョン出版 | 2017.12 |
| 91 | 松村 昌廣 | 衰退する米国覇権システム | 芦書房 | 2017.12 |
| 90 | 清水 由文 | アイルランドの農民家族史 | ナカニシヤ出版 | 2017.12 |
| 89 | 大倉 季久 | 森のサステイナブル・エコノミー | 晃洋書房 | 2017.11 |
| 88 | 信夫 千佳子 | 文眞堂 | 2017.9 | |
| 87 | 谷口照三・石川明人・伊藤潔志(編著) | 自由と愛の精神—桃山学院大学のチャレンジ | 大学教育出版 | 2016.11 |
| 86 | 中村 恒彦 | 会計学のイデオロギー分析 | 森山書店 | 2016.12 |
| 85 | 李羲準・李羲平(著)
梅山 秀幸(訳) |
渓西野譚 | 作品社 | 2016.12 |
| 84 | 松村 昌廣 | 米国覇権の凋落と日本の国防 | 芦書房 | 2015.11 |
| 83 | 全 在 紋 | 会計の力 | 中央経済社 | 2015.10 |
| 82 | 青野 正明 | 帝国神道の形成 —植民地朝鮮と国家神道の論理 | 岩波書店 | 2015.7 |
| 81 | 石田 あゆう | 戦時婦人雑誌の広告メディア論 | 青弓社 | 2015.1 |
| 80 | 松澤 俊二 | 「よむ」ことの近代 —和歌・短歌の政治学— | 青弓社 | 2014.12 |
| 79 | 竹原 憲雄 | 日本型ODAと財政 —構造と軌跡— | ミネルヴァ書房 | 2014.12 |
| 78 | 南出 和余 | 「子ども域」の人類学 | 昭和堂 | 2014.10 |
| 77 | 石田 易司・竹内 靖子
野口 和行 |
晃洋書房 | 2014.7 | |
| 76 | 片平 幸 | 日本庭園像の形成 | 思文閣出版 | 2014.3 |
| 75 | 成 俔 著(著)
梅山 秀幸(訳) |
慵斎叢話 | 作品社 | 2013.11 |
| 74 | 竹中 暉雄 | 明治五年「学制」 —通説の再検討— | ナカニシヤ出版 | 2013.1 |
| 73 | 寺田 友子 | 住民訴訟判例の研究 | 成文堂 | 2012.12 |
| 72 | 津田 直則 | 社会変革の協同組合と連帯システム | 晃洋書房 | 2012.8 |
| 71 | 竹内 真澄 | 物語としての社会科学 | 桜井書店 | 2011.12 |
| 70 | 宮本 孝二 | 吉本隆明の社会理論 | 晃洋書房 | 2011.11 |
| 69 | 李斉賢、徐居正(著)
梅山 秀幸(訳) |
櫟翁稗説・筆苑雑記 | 作品社 | 2011. 3 |
| 68 | 竹歳 一紀・藤田 香(編著) | 晃洋書房 | 2011. 1 | |
| 67 | 松村 昌廣 | 東アジア秩序と日本の安全保障戦略 | 芦書房 | 2010.12 |
| 66 | 厳 善平 | 中国農民工の調査研究 | 晃洋書房 | 2010.12 |
| 65 | 鈴木 富久 | 大月書店 | 2010.11 | |
| 64 | 鈴木 富久 | グラムシ『獄中ノート』の学的構造 | 御茶の水書房 | 2009.10 |
| 63 | 松村 昌廣 | 芦書房 | 2008.12 | |
| 62 | 牧野 丹奈子 | 晃洋書房 | 2008.8 | |
| 61 | Koji ARIKAWA | A Reference Guide of Diagnostics for the Generative Syntax —Data from English,Hindi,and Japan— | 三恵社 | 2008 |
| 60 | Hideya YAMAKAWA | Visible and Invisible in Greek Philosophy | University of Press of America | 2008 |
| 59 | Leonard Blusse(著)
深見純生・藤田加代子
小池 誠(訳) |
竜とみつばち —中国海域のオランダ人400年史— | 晃洋書房 | 2008.3 |
| 58 | 佐賀 朝 | 近代大阪の都市社会構造 | 日本経済評論社 | 2007.12 |
| 57 | 谷口 照三 | 文眞堂 | 2007.9 | |
| 56 | 望月 和彦 | 大正デモクラシーの政治経済学 | 芦書房 | 2007.1 |
| 55 | 瀧澤 仁唱 | 障害者間格差の法的研究 —格差法認と自立支援— | ミネルヴァ書房 | 2006.12 |
| 54 | 石田 易司 | オーストラリアの野外レクリェーション | エルピス社 | 2006.11 |
| 53 | 深沢 徹 | 森話社 | 2006.11 | |
| 52 | 柳夢寅(著)
梅山 秀幸(訳) |
於于野譚 | 作品社 | 2006.8 |
| 51 | 松永 俊男 | ダーウィン前夜の進化論争 | 名古屋大学出版会 | 2005.12 |
| 50 | 小池 誠 | 東インドネシアの家社会学会 —スンバの親族と儀礼— | 晃洋書房 | 2005.12 |
| 49 | 竹歳 一紀 | 中国の環境政策 —制度と実効性— | 晃洋書房 | 2005.12 |
| 48 | 松村 昌廣 |
動揺する米国覇権 | 現代図書 | 2005.11 |
| 47 | 厳 善平 | 勁草書房 | 2005.11 | |
| 46 | 一ノ瀬 篤 (編著) | 現代金融・経済危機の解明 | ミネルヴァ書房 | 2005.10 |
| 45 | 志保田 務 | 日本における図書館目録法の標準化と目録理論の発展に関する研究 | 学芸図書 | 2005.5 |
| 44 | 松村 昌廣 | 軍事情報戦略と日米同盟 ─C4ISRによる米国支配— | 芦書房 | 2004.12 |
| 43 | 全 在 紋 | 会計言語論の基礎 | 中央経済社 | 2004.7 |
| 42 | 志保田 務・山田 忠彦
赤瀬 雅子 (編著) |
学芸図書 | 2003.12 | |
| 41 | 金城 盛紀 | シェイクスピアの喜劇 —逆転の願い— | 英宝社 | 2003.5 |
| 40 | 佐々木 宏 | 同文舘 | 2001.7 | |
| 39 | 高田 里惠子 | 文学部をめぐる病い —教養主義・ナチス・旧制高校— | 松籟社 | 2001.6 |
| 38 | 松村 昌廣 | 勁草書房 | 2000.9 | |
| 37 | 徐 龍 達・遠山 淳
橋内 武 (編著) |
多文化共生社会への展望 | 日本評論社 | 2000.5 |
| 36 | 中田 信正 | 同文舘 | 2000.5 | |
| 35 | 梅本 哲世 | 戦前日本資本主義と電力 | 八朔社 | 2000.2 |
| 34 | 日下 隆平 | イェイツとその周辺 | 大学教育出版 | 1999.12 |
| 33 | 松村 昌廣 | 日米同盟と軍事技術 | 勁草書房 | 1999.7 |
| 32 | 鈴木 幾多郎 | 文眞堂 | 1999.3 | |
| 31 | 上田 修 | ミネルヴァ書房 | 1999.3 | |
| 30 | 芝村 篤樹 | 日本近代都市の成立 —1920・30年代の大阪 | 松籟社 | 1998.12 |
| 29 | 稲別 正晴 (編著) | ホンダの米国現地経営 —HAMの総合的研究— | 文眞堂 | 1998.5 |
| 28 | 厳 善平 | 中国農村・農業経済の転換 | 勁草書房 | 1997.9 |
| 27 | 林 錫 璋 | 債権と担保 | 法律文化社 | 1997.1 |
| 26 | 松永 俊男 | ダーウィンの時代—科学と宗教— | 名古屋大学出版会 | 1996.11 |
| 25 | 滝澤 武人 | 福音書作家マルコの思想 | 新教出版社 | 1995.12 |
| 24 | 熊谷 次郎 | ミネルヴァ書房 | 1995.1 | |
| 23 | 竹中 暉雄 | 囲われた学校—1900年 —近代日本教育史論— | 勁草書房 | 1994.10 |
| 22 | 池野 茂 | 琉球山原船水運の展開 | ロマン書房本店 | 1994.1 |
| 21 | 戦後日本経済研究会(編著) | 大恐慌と戦間期経済 | 文眞堂 | 1993.11 |
| 20 | 西村 徹 | オーウェルあれこれ | 人文書院 | 1993.10 |
| 19 | 鈴木 健 | 独占資本主義の研究 | 文眞堂 | 1992.9 |
| 18 | 中村 祥子 | E.ギャスケルの長編小説 | 三友社出版 | 1991.11 |
| 17 | K.I.Boudouris(著)
山川 偉也(訳) |
正義・愛・政治 | 勁草書房 | 1991.1.1 |
| 10 | 赤瀬 雅子・志保田 務 | 永井荷風の読書遍歴 —書誌学的研究— | 荒竹出版 | 1990.2 |
| 15 | 勝部 元(編著) | 現代世界の政治状況 —歴史と現状分析— | 勁草書房 | 1989.3 |
| 14 | 山本 紀徳 | 決定と計画の数理分析 | 勁草書房 | 1989.2 |
| 13 | 戦後日本経済研究会(編著) | 日本経済の分水嶺 | 文眞堂 | 1988.11 |
| 12 | 竹中 暉雄 | ヘルバルト主義教育学 —その政治的役割— | 勁草書房 | 1987.2 |
| 11 | 山川 偉也 | ギリシア人の哲学と世界観 | 玉川大学出版部 | 1986.12 |
| 10 | 岡田 章子 | キーツの詩 | あぽろん社 | 1986.12 |
| 9 | 西川 一廉 | 職務満足の心理学的研究 | 勁草書房 | 1984.9 |
| 8 | 安元 稔 | イギリスの人口と経済発展 —歴史人口学的接近— | ミネルヴァ書房 | 1982.12 |
| 7 | T. J.Gorton(著)
谷口 勇(訳) |
アラブとトルバドゥ-ル
—イブン・ザイドゥ-ンの比較文学的研究— |
芸立出版 | 1982.8 |
| 6 | 鳥越 皓之 | トカラ列島社会の研究 —年齢階梯制と土地制度— | 御茶の水書房 | 1982.7 |
| 5 | 足立 明久 | 勁草書房 | 1982.10 | |
| 4 | 津田 直則
山本 紀徳
鈴木 幾多郎
竹浪 祥一郎 |
計画と市場 —社会主義経済の新展開— | 勁草書房 | 1981.12 |
| 3 | チョ キジュン (著)
徐 龍 達 (訳) |
近代韓国経済史 | 高麗書林 | 1981.12 |
| 2 | J.E.King (著)
小川 登 (訳) |
労働経済学入門 | ミネルヴァ書房 | 1978.12 |
| 1 | 赤瀬 雅子 | 永井荷風とフランス文学 | 荒竹出版 | 1976.4 |