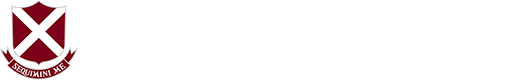第9回 『私たちはなぜ家を買うのか——後期近代における福祉国家の再編とハウジング』
村上あかね(社会学部 社会学科教授)
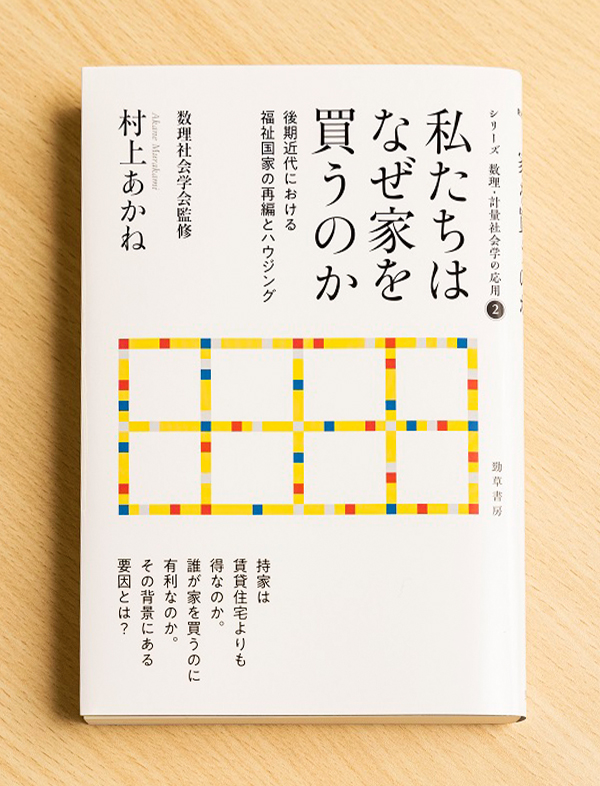
日本の持家率は6割ですので、持家に住む人のほうが賃貸住宅に住む人よりも多いといえます。なぜ私たちは家を所有したがるのでしょうか。その背景を日本の住宅政策の変遷や欧米との対比から考察したのが『私たちはなぜ家を買うのか——後期近代における福祉国家の再編とハウジング』(勁草書房)です。社会学部の村上あかね教授に、本書について聞きました。
■家を所有することを当然とみなす社会の構造に迫る
今回紹介する著書『私たちはなぜ家を買うのか——後期近代における福祉国家の再編とハウジング』は、2023年12月に発行されました。タイトルにある「なぜ家を買うのか」という根源的な問いに、まず興味を持ちました。家の所有に、そもそも関心を持たれたきっかけを教えてください。
賃貸住宅でも持家でも、人が住む場所であることに変わりはないはずです。戦前の日本、とくに都市部では借家が圧倒的多数でした。ところが、日本をはじめ多くの国では、戦後すぐあるいは高度経済成長期以降は家を買うことが望ましいと多くの人がみなすようになりました。それがなぜか、問題はないのか、取り組む必要がある課題だと考えました。結論をいえば、家を持つことが有利になるような住宅政策が展開されていきました。
私は大学時代に阪神・淡路大震災を経験しており、地震の多い日本で家を持つことはリスクがあること、またそのリスクは住宅がある場所によって異なることに気づきました。そのことが、住宅問題を考える一つのきっかけになっています。
 今回は、村上先生の研究室でお話を伺いました
今回は、村上先生の研究室でお話を伺いました
本書を読み、日本での住宅取得には妻の就業の有無が影響しなかったり、生前贈与は長男が受け取りやすいわけではなかったりしたことが意外でした。
日本の男女間賃金格差の大きさや性別役割分業意識の強さを考えれば、妻の就業の有無が住宅の取得に影響しないのは予想されていた結果です。ただし、海外の研究者には驚かれます。親子間でのさまざまなやりとりが必ずしも長男優先でなくなっていることは、日本のほかの研究でも海外の研究でも同じような結果が得られています。このように研究を積み重ねることで日本の家族も世界の家族もそのような方向に変化している、とより確実に言えるようになったと理解していただけると嬉しいです。
■オランダから学ぶこと
本書では、海外の事例も紹介されています。村上先生が特にオランダに注目してご研究されている理由は何ですか。
オランダも持家が多い社会ですが、依然として公的賃貸住宅(社会賃貸住宅)が充実しています。それを支える社会の仕組みに興味を持ちましたが、日本では研究がまだ少ないからです。そこで、サバティカルではライデン大学に滞在しました。
日本がオランダに見習うべきところはどのような点ですか。
本書のテーマである住宅政策という点でいえば、オランダでも1970年代から持家政策に転換しており、現在は持家が主流の社会です。そのため、公的賃貸住宅は低所得層向けになりつつありますが、それでも公的賃貸住宅に対するスティグマ(偏見や差別)が小さく、また条件を満たしていれば入居者は家賃補助を受けられることは日本との大きな違いです。割り当て数は少ないですが、中・高所得層も公的賃貸住宅に入居できます。日本にも生活保護の家賃扶助や住居確保給付金がありますが、対象者は多くありません。日本の家賃補助は企業による福利厚生の一環であり、世界的には例外的です。また、大企業に勤める正社員ほど家賃補助や社宅などの恩恵を受けることができ、もともと存在していた格差をさらに拡大させることになるといえます。したがって、私は日本の企業福祉は見直す時期に来ていると思っています。
 持家が主流のオランダでも、国民の意識は日本と大きく異なる
持家が主流のオランダでも、国民の意識は日本と大きく異なる
そのほかに、オランダは世界で初めて同性婚を認めたこと、子どもの有無にかかわらず労働時間が短くゆとりがあること、公園が充実していることなど、社会全体が平等で寛容であることも見習いたい点ですね。小さい頃から夜遅くまで勉強して良い大学に入って良い企業に入ることだけが重視される社会ではありません。選択肢も多く、大学入学後も退学して別の学校に再入学したり、働いてから大学に入学したりするなどやり直しができる社会のように映りました。子どもの意思は尊重されますが、「自己責任」という言葉は聞いたことがありません。このような社会の背景には、キリスト教精神(カルヴァニズム)、人々の多様な意見が反映されやすい他党連立型の政治構造、「学校闘争」によって権利を勝ち取ってきた歴史があります。人々は王室や政府に対しても率直に批判をします。
 オランダの街並み(シーボルトハウス)
オランダの街並み(シーボルトハウス)
終章では、「持家を重視する政策を見直し、人びとが多様な選択をできるようにする」「公的な家賃補助を増やす」など、より良い住生活を実現させるための6つの提案が書かれています。こうした提案を受けて、私たちは何をすべきでしょうか。
選挙権があるならば、投票することができます。選挙権がなくても、政治家に自分の意見を伝えたり、SNSで自分の意見を発信したりすることができます。最近はSNS上でハッシュタグ「#」をつけて自分の意思を示す「ハッシュタグ・アクティビズム」が行われています。行動しないと何も変わらないですからね。
この本の一番のセールスポイントは何でしょうか。
ハウジングに関する欧米の理論を体系的に紹介したことと、オランダに住む人たちの生の声を紹介したことです。オランダに滞在した当初は受け入れ先の先生しか知り合いがいませんでしたが、積極的に出かけて友人を作り、多くの方のご自宅を訪問したりしてお話を聞きさらに人をご紹介いただきました。帰国後には、オランダ語教室に通って勉強もしました。その後もライデン大学の関係者に誘われて新蘭日日蘭事典のボランティアをしていますが、なかなか上達しません。
 オランダの街並み(ライデン市)
オランダの街並み(ライデン市)
本を出版してからの反響はいかがでしたか。
調査協力者の方やこれまで支えてくださった方々にお礼とともに拙著をお渡しすることができて、喜んでくださったことがうれしかったです。紀伊国屋書店ではマシュー・デスモンドの『家を失う人々 最貧困地区で生活した社会学者、1年余の記録』(海と月社)と並べて置いてくださったと聞きました。研究者だけではなく、研究者以外の方にも「読みやすい」 と言っていただいたことで、ほっとしました。編集者や研究仲間、家族のおかげです。出版事情が厳しい折、本学の出版助成を受けることができたので安心して書くことができました。
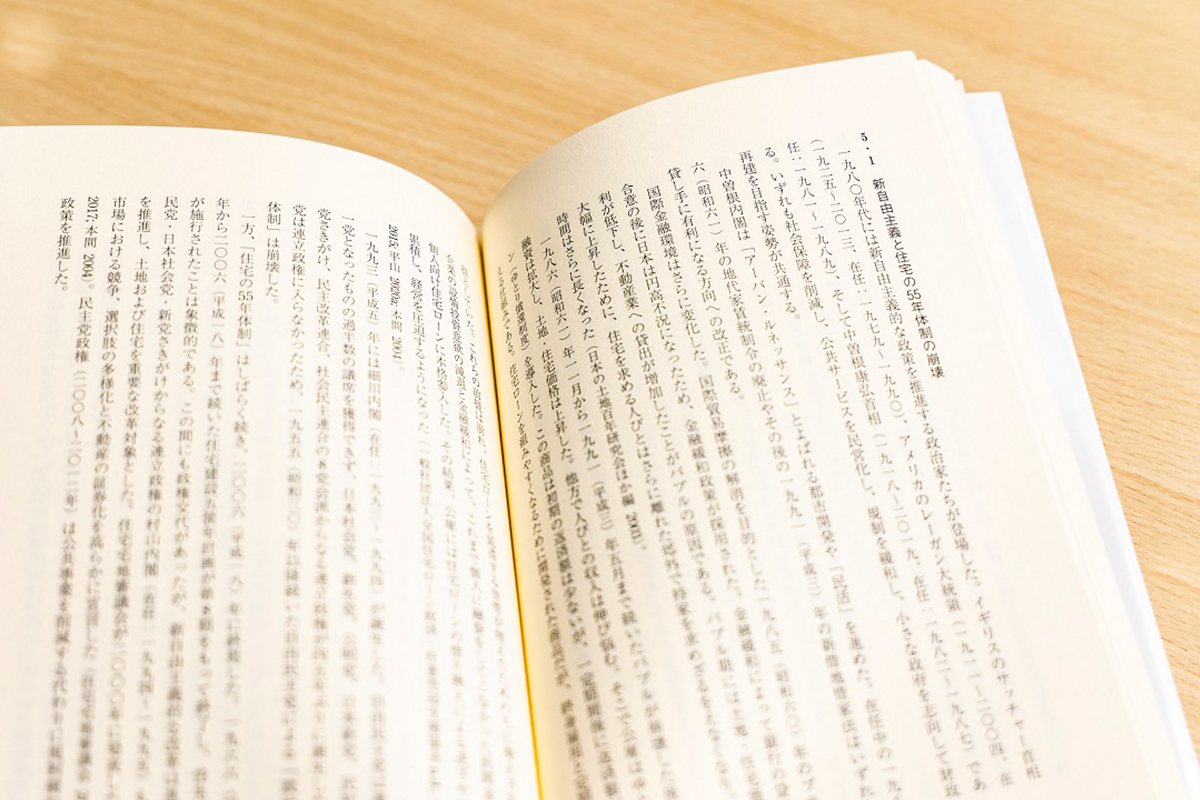 調査に協力してくださったオランダの方々の声をはじめ、様々な想いが詰まった一冊になりました
調査に協力してくださったオランダの方々の声をはじめ、様々な想いが詰まった一冊になりました
■データ分析とインタビューから社会を把握
本書は大規模なデータ分析とインタビューから、住宅所有を促す要因を解明しておられます。どのようなご苦労がありましたか。
大規模なデータ収集をするためにはチームで協力して大型の研究費を獲得する必要があります。データを収集した後も、統計ソフトを用いて分析を行うまでにはデータの論理矛盾をチェックしたり、整理したりする作業が欠かせません。料理でいえば下ごしらえに相当するのですが、大変地味な作業です。また、予想しない結果が得られた時にその理由を考えたり、そのメカニズムを考えながら、分析を何度もやり直したり、結果を解釈することには苦労があります。これらの苦労は、コンピューターが発達してもあまり変わらないと思います。 インタビュー調査では対象者を探すこと、対象者の反応を見て臨機応変に質問をしていくこと、またそれをどうやって分析するかが難しいですね。 多くの方々の協力があってのことですので、研究成果を広く社会に還元することが研究者の社会的責任だと自覚しています。
 村上先生の研究室では、随所にオランダを感じられる
村上先生の研究室では、随所にオランダを感じられる
現代の情報社会では、データを収集し分析する力が求められています。学生には、どのような力をつけてほしいとお考えでしょうか。
質問紙(いわゆるアンケート)などで収集した量的データやインタビューなどで収集した質的データの両方について、科学的な手続きに従ってデータを収集して分析する力を身につけてほしいです。理論から論理的に仮説を導き、自分の予想しない結果が得られても考え抜くこと、そして研究倫理に配慮することも非常に重要です。 2024年度から、桃山学院大学和泉キャンパスの学生を対象に学部の垣根を超えてデータサイエンティストを育成するプログラム「スーパーデータサイエンスプログラム(SDP)」が始まりました。私は協力教員として、公的統計の活用や研究倫理などを話す予定です。
村上先生のご専門である家族社会学、社会階層論の面白さは、どこにあると思われますか。
歴史を振り返ったり、他国と比較したりすることで家族というものを相対化して捉えることが面白いです。拙著のあとがきにも書きましたが、社会階層論は不平等や格差の問題を理論的に捉える枠組みがあることです。
現在、取り組んでおられる研究や、今後の抱負を教えてください。
今、取り組んでいる研究は、若者の住宅問題と親子関係です。これは、少子高齢化問題を解くカギの一つになります。その一部は、今年の9月にミネルヴァ書房から『大学生から見るライフコース(仮題)』として刊行される予定です(共編著)。空き家が多い日本で暮らしていると想像しにくいのですが、移民が多いヨーロッパでは住宅不足が深刻で住宅価格が高騰しているため、若者が親元にとどまるようになっています。「課題先進国」日本に関する知見は世界の研究者や政策関係者にとって必要とされているはずですので、次は英語で論文を書き、本にまとめたいです。

プロフィール
むらかみ・あかね/1974年、福島県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間科学)。主著に『災禍の時代の社会学』(共著、東京大学出版会、2023年)、『家族研究の最前線5 家族のなかの世代間関係』(共著、日本経済評論社、2021年)、『人生の歩みを追跡する──東大社研パネル調査でみる現代日本社会』(共著、勁草書房、2020年)、『論点ハンドブック 家族社会学』(共著、世界思想社、2009年)、『女性たちの平成不況──デフレで働き方・暮らしはどう変わったか』(共著、日本経済新聞社、2004年)がある。専門は家族社会学、社会階層論、社会調査法、比較社会論(オランダ)。