社会の中でどのように法が活用されているかを実務家の講義やグループワークを通じて考える「法学特講—社会の中の法体験C」が始まり、法学部生と大学の授業受講を希望する高校生が参加しています。通常の授業では感じられない「現実」に触れ、改めて社会における「法」 を考えるため、本年度は、地方行政と地方公務員を中心にグループワークで議論します。
7月30日(火)の最初の講義とグループワークのテーマは「日本の市史編さん事業・文化財行政:地方公共団体の役割」です。大阪府和泉市教育委員会生涯学習部文化遺産活用課の村上絢一主事に講師をお願いしました。
村上主事は大学・大学院で日本中世史を専攻し、学芸員資格も取得しておられます。「行政は法律に基づいて行われ、文化財行政も例外ではありません」と、教育基本法や社会教育法、文化財保護法、地方公務員法などの条文を紹介しながら、市教委が取り組んでいる文化財行政や市史編さん事業に関する法律について解説しました。また和泉市には文化遺産活用課が所管する施設として、「和泉市いずみの国歴史館」、「池上曽根史跡公園」、「信太の森の鏡池史跡公園」という「公の施設」があり、すべて市条例に基づいて設置されていることを説明しました。
講義のあと、受講生は市役所本庁舎のオフィスや市役所別館の市史編さん室、土器や古文書などの歴史資料を展示・保存している和泉市いずみの国歴史館を見学し、文化財保護行政の実務の一端に触れました。
◇高校生も参加してグループワーク
講義と見学を踏まえて、▽なぜ文化財を保存し活用する必要があるのか、▽文化財行政の課題と解決策——をテーマにグループワークに取り組みました。大学生と高校生が混合で4、5人のグループ6班を作り、自由に考えついたアイデアをメモ用に書き出して議論し、模造紙に自分たちの結論をまとめました。
学生らは、▽歴史を学んで教訓を得ることが出来る、▽観光への活用が地域経済活性化につながる、▽国際交流の懸け橋になる——などの理由で、文化財の保存と活用の必要性を強調しました。さらに、講義と見学で感じた課題として、▽遺跡から出土した遺物の保管場所が足りない、▽予算が足りない、▽文化財の価値が知られていない、▽文化財保護に取り組む人材が不足している——などを挙げ、クラウドファンディングや文化財施設の来館者増の取り組み、学校教育の場で文化財の価値や魅力を伝えることなどを提言しました。
村上主事は「文化財行政は、地方行政の中でも一般にはなじみの薄い分野だが、福祉など他の分野と同様、法律に基づいて行われていることをお話ししました。受講態度も良く、熱心に取り組んでいたことが印象的でした。大学生は幅広い視点でグループワークの議論をリードしており、大学での学びの蓄積を感じました」と話していました。また、大学の授業に参加した高校生は「長時間をかける本格的なグループワークは初めてでしたが、大学生が議論をリードしてくれました。大学の学びで成長できるんだな、と実感できました」と振り返っていました。
法学特講は7月25日(木)にリモートでオリエンテーションを行った後、7月30日(火)、8月6日(火)、7日(水)の3日間、1日5コマ(最終日は4コマ。各90分)の講義、施設見学、グループワークに取り組みます。 8月6日(火)は水道行政、8月7日(水)は警察行政をテーマに、現場で活躍しておられる実務家の生の声をうかがいます。

和泉市教育委員会の村上主事に講師を務めていただきました
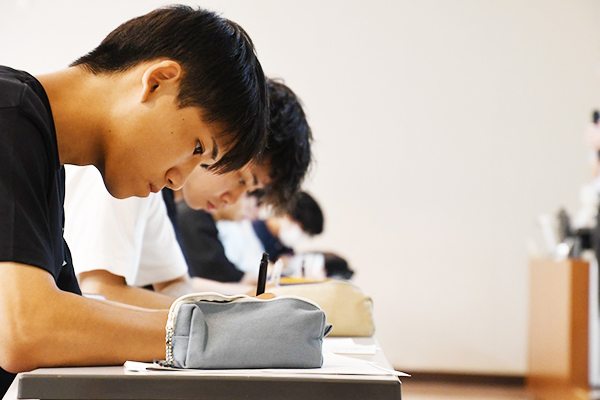
講義の様子

講義では、市内の関係施設を見学させていただきました


グループワークの様子
