

グローバル社会の課題に取り組み、意見を英語で発信できる国際コミュニケーターの育成

異文化コミュニケーション能力を活かし、世界の人々との対話と交流で、共生社会の実現に貢献する人材の育成

言語と文化の理解を通じて幅広い視野を身につけ、平和な社会の実現に貢献する人材の育成
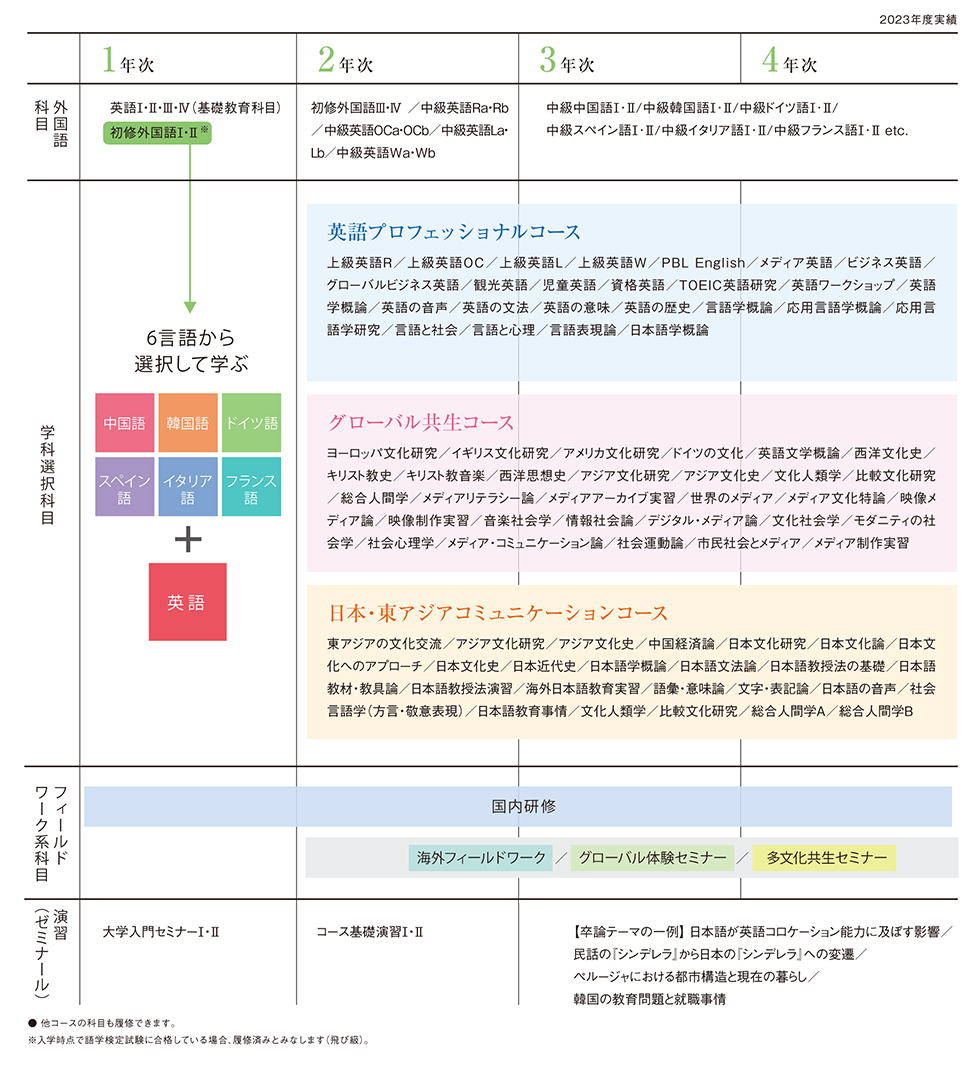
 大阪市内のモスク「Masjid Istiqlal Osaka (MIO)」でのフィールドワークなどを通して異文化共生について考えています。モスクでは、バングラデシュ人カップルのイスラーム式結婚式を見学し、新婦や参列者にイスラームについてインタビューを実施。モスクの歴史やイスラームの教えについてお話を伺い、理解を深めました。
大阪市内のモスク「Masjid Istiqlal Osaka (MIO)」でのフィールドワークなどを通して異文化共生について考えています。モスクでは、バングラデシュ人カップルのイスラーム式結婚式を見学し、新婦や参列者にイスラームについてインタビューを実施。モスクの歴史やイスラームの教えについてお話を伺い、理解を深めました。
また、大学のある和泉市で、パキスタン出身の方が主催した「エクタディ」というイベントに参加し、フィールドワークを実施。主催者の出身地であるシンド州の祭典を再現したイベントには、和泉市や関西在住のパキスタン人が集まったほか、地元の青年団も参加。パキスタン人の子どもたちが地車囃子を体験する様子の見学などを通じて、国際交流のあり方を学びました。(担当教員 小池誠)
この授業では「Osakaの寺社を学ぶ、歩く」をテーマに、四天王寺や住吉大社を訪れる学外演習を通じて、大阪の寺院や神社について英語で学びます。授業では、基礎知識の習得に加え、留学生と日本人学生が交流する機会を設け、妖怪双六や連歌作りといったグループ活動も行っています。お寺や神社のほかにも「いずみの国歴史館」や「かたなの博物館」を訪れ、学芸員や刀研師の方に学ぶ機会を得て、理解を深めています。(担当教員 南郷晃子)
 この授業では、韓国の大学生とオンラインで繋がり、日韓混合グループを作ってチームプロジェクトを進めます。これまでの授業では、「地方都市の魅力をどう伝えるか」というテーマで地域の魅力(文化、観光、食など)を考え効果的に海外の人々に発信する方法を探り、実際に市職員の方に提案するなどしました。韓国でヒットした映像コンテンツを日本向けにローカライズし成果物を発表するなど、多様なテーマに日韓の学生が協働して取り組んでいます。(担当教員 新保朝子)
この授業では、韓国の大学生とオンラインで繋がり、日韓混合グループを作ってチームプロジェクトを進めます。これまでの授業では、「地方都市の魅力をどう伝えるか」というテーマで地域の魅力(文化、観光、食など)を考え効果的に海外の人々に発信する方法を探り、実際に市職員の方に提案するなどしました。韓国でヒットした映像コンテンツを日本向けにローカライズし成果物を発表するなど、多様なテーマに日韓の学生が協働して取り組んでいます。(担当教員 新保朝子)
本授業は三部構成となっており、まず中国の大学生と混合グループを組み、日本と中国の文化について話し合ったうえでテーマを決め、オンラインで計4回程度の共同発表を行います。 続いて、中国の日本企業で働く中国人や、中国在住の日本人を招いたオンライン講演会を複数回開催し、現地での生活や職場文化について学びます。最後には、教員の講義や学生によるグループ発表を行います。本授業では、日本と中国の文化や社会を多角的に学び、国際的な視点を養います。(担当教員 王其莉)
この授業では、日本とフランスの芸術交流史を学び、文化の混じり合いを自分の言葉で表現する力を養います。これまでに、大阪中之島美術館「クロード・モネ 連作の情景」展や中之島香雪美術館「北斎・広重」展などで学外授業を実施しました。履修者はまず「ジャポニスム」に関する講義で基礎知識を得た後、ワークシートを使って展示作品を体験。教室では西洋絵画と日本の浮世絵の特徴や影響について議論し、構図や色彩を比較しました。最後に、各自が選んだテーマで調査結果をパワーポイントにまとめて発表。少人数授業の利点を活かし、自分らしい言葉で異文化交流の歩みについて解説する力を深めました。(担当教員 宮脇永吏)
 本授業では地域フィールドワークを行い、各地域特有の文化や歴史の理解を深め、オリジナルな視点から伝えるメディア作品づくりに取り組んでいます。写真や動画、音声などのメディア表現技術を学び、フィールドワークでの気づきや学びを、自己語り動画「デジタルストーリーテリング」のメソッドで作品化します。これまで、世界遺産に登録されている奈良・吉野山を巡って食文化を取り上げたり、神戸の移住ミュージアムや旧居留地、南京町を訪れて多文化の歴史をテーマにした作品作りを行いました。(担当教員 土屋祐子)
本授業では地域フィールドワークを行い、各地域特有の文化や歴史の理解を深め、オリジナルな視点から伝えるメディア作品づくりに取り組んでいます。写真や動画、音声などのメディア表現技術を学び、フィールドワークでの気づきや学びを、自己語り動画「デジタルストーリーテリング」のメソッドで作品化します。これまで、世界遺産に登録されている奈良・吉野山を巡って食文化を取り上げたり、神戸の移住ミュージアムや旧居留地、南京町を訪れて多文化の歴史をテーマにした作品作りを行いました。(担当教員 土屋祐子)
 韓国に興味のある学生と韓国人留学生が参加する課外活動を毎週1回、3人の教員が交代で開催しています。「韓国語と日本語の漢字語」や「韓国語の方言」などテーマ別の勉強会や、韓国から来た大学教授との異文化ディスカッションに加え、韓国の伝統遊びユンノリや、夏の韓国かき氷、正月のトック(韓国雑煮)作りなど、韓国文化を体験するイベントも行いました。(担当教員 青野正明・新保朝子・韓娥凜)
韓国に興味のある学生と韓国人留学生が参加する課外活動を毎週1回、3人の教員が交代で開催しています。「韓国語と日本語の漢字語」や「韓国語の方言」などテーマ別の勉強会や、韓国から来た大学教授との異文化ディスカッションに加え、韓国の伝統遊びユンノリや、夏の韓国かき氷、正月のトック(韓国雑煮)作りなど、韓国文化を体験するイベントも行いました。(担当教員 青野正明・新保朝子・韓娥凜)
各科目の講義内容は「講義計画(シラバス検索)システム」でご覧いただけます。
キーワード検索欄に科目名称を入れてください。
※講義内容は在学生向けのものです。入学年度の講義内容は変更になる場合があります。