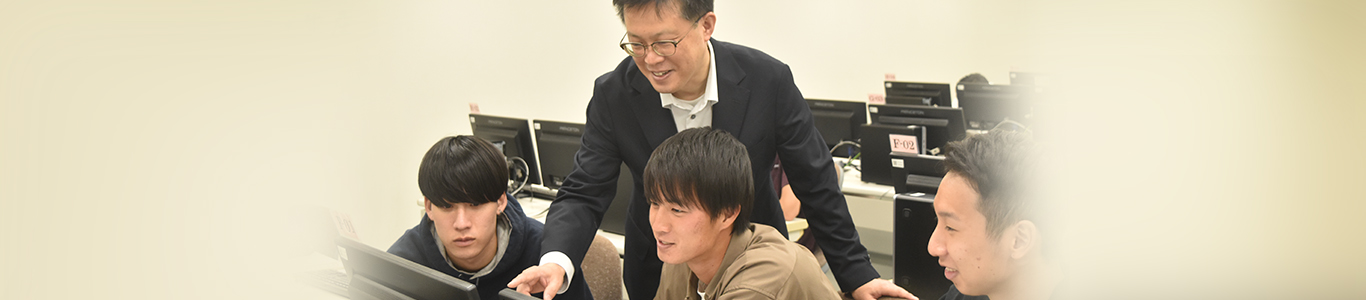
2026年4月より新たに4つ目の分野「金融リテラシー&データ分析養成分野」がスタートします。
経済学部には、歴史、政策、財政、統計、実証、金融、環境、労働、思想、国際関係、アジア、中小企業など、多様で幅広い科目や学問領域が展開されています。
こうした豊かな学びの中で、学生一人ひとりが自身の興味や将来像に合った科目を見つけやすくするために、近年注目されている4つの分野をピックアップし、おすすめ科目としてパッケージ化しました。
このたび新たに加わる「金融リテラシー&データ分析養成分野」では、金融、証券、資産運用などのテーマを中心に、長期的なライフプランや資産運用を含めた金融知識に加えて、株価や金利などの金融データの読み解き方・活用法も身につけます。
経済学部では、学生の皆さんが「何を学ぶか」「どの授業を選ぶか」に迷わず、自分らしい学びを深められるよう、これからも魅力的な学びの環境を提供してまいります。
きっと、あなたの好奇心を満たす科目がここにあります。




井田大輔教授(経済学部 経済学科)の論文が学術雑誌『The North American Journal of Economics and Finance』に採択されました
>詳細はこちら
井田大輔教授、上ノ山賢一准教授(ともに経済学部 経済学科)の共著論文が海外査読付き雑誌『Macroeconomic Dynamics』に採択されました。
>詳細はこちら
【参考URL】
経済学のジャーナルランキング
https://ideas.repec.org/top/top.journals.simple.html
井田大輔教授(経済学部 経済学科)の論文「Optimal Monetary Policy Rules in a Behavioural New Keynesian Model」が、国際的に評価の高い査読付き学術誌『Oxford Bulletin of Economics and Statistics 』に採択されました。
>詳細はこちら
【参考URL】
経済学のジャーナルランキング
https://ideas.repec.org/top/top.journals.simple.html
井田大輔教授、星野聡志准教授(ともに経済学部 経済学科)の共著論文が査読付き学術雑誌『Economic Modelling』に採択されました。
>詳細はこちら
【参考URL】
経済学のジャーナルランキング
https://ideas.repec.org/top/top.journals.simple.html
1月19日(日)、経済学部の吉弘憲介ゼミ(地域政策)の学生3名が、大阪副首都推進局の大学連携プロジェクト成果発表会に参加しました。当日は「2025大阪・関西万博〜ソフト・レガシーと地域間連携の創出〜」をテーマに発表を行い、全国アンケート調査(600サンプル)のデータを分析した成果が評価を受けました。
大阪府・大阪市では「副首都・大阪」の実現を目指しており、関西を中心とする6大学の学生が副首都ビジョンに関連する社会課題について考える「学生リサーチプレゼンテーション」を行いました。
吉弘ゼミではこれまでも、「うめきた2期計画で街はどう変わるのか」「IRの地域経済への影響」「コロナによる大阪地域経済への影響」などのテーマに取り組んできました。今回は2025年大阪・関西万博を取り上げ、全国600サンプルのアンケート調査(桃山学院大学倫理審査番号68番取得)を基に、定量的分析を実施しました。その結果、大阪・関西万博に対する30代以下の期待度が、40代以上の年齢層と比較して統計的に有意に高いことを明らかにし、メディア戦略などへの具体的提案につなげる方向性を提案しました。
万博をテーマの中心に据えた報告を行ったのは桃山学院大学のみで、審査委員の一人から「専門的かつ学術的にも価値が高い調査」と高い評価をいただきました。大阪・関西万博に関心のある多くの聴衆からも興味を持たれ、分析結果は高い関心を集めました。
発表を終えた学生たちは「この万博は、私たちが暮らす大阪・関西地域における国際的なイベントですが、運営上の課題も指摘されています。そこで、この事業をどのように地域や日本経済にプラスに結びつけるか、そのヒントを明らかにすることを目的としてテーマを設定しました。博覧会協会へのメール調査や全国600サンプルのアンケートデータを活用し、10代〜30代と40代以上の間で万博に対する期待に明確な意見の違いがあることが判明しました。若年層ほど万博に期待しているという結論に基づき、万博を盛り上げるための政策提案を行いました」と振り返りました。
吉弘教授は「今回、限られた練習時間の中でアドリブも交えつつ、一生懸命に発表を行う学生たちの姿に成長を感じました。他大学や外部の場で発表することで、新たな視点を得るとともに、自信にもつながったと思います。少人数の3名で協力して成果を出したことに対し、『まずはお疲れ様』と声をかけたいです」と話していました。
<当日の様子>


井田大輔教授、星野聡志准教授(ともに経済学部 経済学科)の共著論文が査読付き学術雑誌『Economic Modelling』に採択されました。
>詳細はこちら
【参考URL】
経済学のジャーナルランキング
https://ideas.repec.org/top/top.journals.simple.html

経済学部を今春卒業された中山虹さん(兵庫県・舞子高校出身)が、令和6年公認会計士試験に見事合格されました。
公認会計士は会計分野の最高峰とされ、日本の三大国家資格の一つに挙げられる難関資格で今年度も約2万人が受験し、合格率はわずか7.4%(昨年度7.6%)でした。
中山さんは高校時代までサッカーに打ち込んでいましたが、大学入学後に新たな目標として公認会計士資格の取得を決意。学業と資格取得のための勉強を両立してこられました。「会社法」などの授業も、大いに役立ったとのことです。
中山さんの努力と成果は、後輩の皆さんにとって大きな励みとなるでしょう。
本当におめでとうございます!
【参考】
▼公認会計士・監査審査会Webサイト
令和6年公認会計士試験の合格発表について
経済学部では、10月15日(火)・16日(水)に現2年次が次年度所属する演習IIIについての学部合同説明会を開催しました。
ブース形式で行われた合同説明会では、担当教員や所属するゼミ学生から演習の特徴について参加学生が説明を受けました。
参加学生は担当教員やゼミ生に積極的に質問していて、盛況な合同説明会となりました。
10月下旬からは各教員の個別説明会が始まり、その後は具体的な応募に向けての書類作成になります。
今回の合同説明会は、教員にとっても学生にとっても有益な場となりました。
残り2年間の経済学部での学びが充実したものとなることを期待します。




井田大輔教授(経済学部 経済学科)の論文が査読付き学術雑誌『The B.E. Journal of Macroeconomics』に採択されました。
>詳細はこちら
【参考URL】
経済学のジャーナルランキング
https://ideas.repec.org/top/top.journals.simple.html
内山ゼミは、2024年2月10日(土)~18日(日)に、ラオス人民民主共和国において4年ぶりに研修を実施しました。
当ゼミは東南アジア経済を専攻する3・4年次ゼミで、研究と並行して、ラオスの小・中学校や高校に、学習教材や学用品、スポーツ用品等を贈呈する「日ラオス友好促進活動」を展開しています。研修ではこの活動に加えて、ラオス国民議会やJETROビエンチャン事務所、JICAラオス事務所を訪問し、ヒアリング学習を行うことで、ラオスについての理解を深められるよう試みています。
研修の詳細や、研修内でのセンビライ小・中学校(ラオス)との親善交流の様子は、下記の記事をご覧ください。
○経済学部 内山ゼミがラオス研修を実施しました
○経済学部 内山ゼミがセンビライ小・中学校(ラオス)と親善交流を行いました
○センビライ小・中学校(ラオス人民民主共和国)より、内山ゼミ(経済学部)「日ラオス友好促進活動」の贈呈物資に対するお礼の手紙を受け取りました
<2023年度ゼミ/ラオス研修の様子>






また、ラオス人民民主共和国のビジネスや投資、観光に関する情報発信サイト「ラオス情報センター」に、内山ゼミの「日ラオス友好促進活動」に関する記事が掲載されています。こちらもぜひご覧ください。
本件に関する問い合わせ先:内山怜和(経済学部)
★教員メッセージ
2024年5月8日(水)に第二回桃山経済研究会(本学経済学部主催)が開催されました。
本研究会は、桃山学院大学経済学部内ひいては学内外との研究交流を通じて、研究・教育活動の活性化をはかることを目的としています。
当日は、本学経済学部の佐藤洋先生と角谷嘉則先生の研究報告が行われました。
【報告①】
佐藤洋(桃山学院大学経済学部専任講師)
「大都市圏郊外の地方税収確保に関する地理学的研究―地理的加重回帰分析の応用可能性」
【報告②】
角谷嘉則(桃山学院大学経済学部教授)
「コミュニティビジネスの設立と変容-京都府南丹市美山町を事例として-」




それぞれ教員の研究報告についての質疑応答も活発に行われ、実りある研究会となりました。
今後も継続的な研究会の開催を通じて、本学経済学部の魅力を発信していきます。
本件に関する問い合わせ先:山川俊和(経済学部)、井田大輔(経済学部)
経済学部の教員が、新聞、テレビ、専門誌、オンラインメディアなど、さまざまなメディアでとりあげられています。
2023年度の主なメディア出演・掲載実績) ※一部抜粋
〇オンライン経済メディア「Business Insider Japan」で吉弘憲介教授(経済学部経済学科)の見解が掲載されました
〇辻洋一郎教授(経済学部経済学科)の見解がNHK総合「ニュースLIVE!ゆう5時」で放送されました
〇米田紘康准教授(経済学部経済学科)の寄稿が『かけはし』(2023年10月号)に掲載されました
〇TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』で辻洋一郎教授(経済学部経済学科)の見解が放送されました
〇月刊『生活経済政策』に山川俊和教授(経済学部経済学科)の寄稿が掲載されました
〇TBSテレビ「news23」で吉弘憲介教授(経済学部経済学科)のコメントが紹介されました
〇学術雑誌『堺研究』に島田克彦教授(経済学部経済学科)の寄稿が掲載されました
2023年度は32のメディアでとりあげられており、教員それぞれが専門分野で活躍しています。
今後も教員の研究成果や社会貢献が期待されます。
2024年3月21日(水)、第一回桃山経済研究会(本学経済学部主催)が開催されました。
本研究会は、桃山学院大学経済学部内、ひいては学内外との研究交流を通じて、研究・教育活動の活性化をはかることを目的としています。
当日は、本学経済学部の梅田百合香教授と吉弘憲介教授の研究報告が行われました。
【報告①】
梅田百合香(桃山学院大学経済学部教授)
「ホッブズとトゥキュディデスの倫理学ー人間本性と戦争についてのヒストリアー」
【報告②】
吉弘憲介(桃山学院大学経済学部教授)
「リヴァイアサンを解体する: 財政ポピュリズムの政治経済学的可能性と限界についてー大阪維新の会の財政運営を題材に」




それぞれ教員の研究報告についての質疑応答も活発に行われ、実りある研究会となりました。
なお、次回、第二回桃山経済研究会は5月8日(水)に開催予定です。
引き続き、本学経済学部の魅力を発信していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
本件に関する問い合わせ先:山川俊和(経済学部)、井田大輔(経済学部)
例えば,薬品の化学反応を観察したり,電流と電磁石の強さとの関係を観察したりといったことをイメージするかもしれません.
さらに,経済学で「実験」と言われて何をイメージしますか?
化学反応から将来の株価を予測するのでしょうか?ビリビリと強い刺激を与えて景気を良くするのでしょうか?どちらも関係なさそうです。
では経済学で行われる実験とは一体どういうものでしょうか?また,実験を行うことで経済学さらには実際の経済にどのような影響を与えるのでしょうか?
8/6(日)のオープンキャンパスの模擬授業では皆さんに実験に参加してもらい,体験を通して経済学で行われる実験を垣間見てもらった上で,実験が経済学や実際の経済をどのように変えようとしているのか説明します。
>【8/6(日)オープンキャンパス模擬授業担当 西﨑勝彦教授からのメッセージ】
